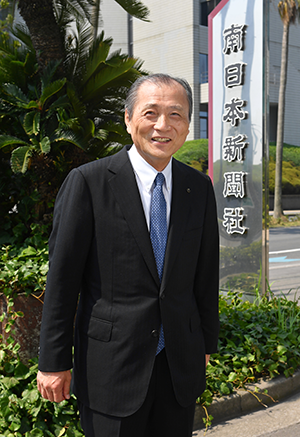 鹿児島をもっと良くしたい。住みやすくしたい。困っている人を減らしたい。悲しむ人もなくしたい。ここで暮らして良かった、助かった―。だれもがそう思えるような地域づくりをもっと進めたい。いつもそう目指しています。
鹿児島をもっと良くしたい。住みやすくしたい。困っている人を減らしたい。悲しむ人もなくしたい。ここで暮らして良かった、助かった―。だれもがそう思えるような地域づくりをもっと進めたい。いつもそう目指しています。
| 初任給 | 22歳 基本給226,070円(2023年4月実績) |
|---|---|
| 各種手当 | 住宅手当、交通手当、家族手当、保険手当など |
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 賞与 | 夏季・冬季 |
| 勤務時間 | 1日8時間(実働7時間)時間帯は配属先によって異なる ※ローテーションによる交代制勤務、フレックスタイム制の職場あり |
| 休日休暇 |
完全週休2日制(年間休日数121~129日) 年次有給休暇 入社時15日、最大24日 リフレッシュ休暇5日、看護休暇、介護休暇など |
| 勤務地 |
本社(鹿児島市) 支社(東京、福岡) 総局・支局(鹿児島、宮崎) |
| その他 | 社会保険、各種福利厚生完備、定年60歳(継続雇用制度あり) |
| 採用者数 | 2024年 男性0人 女性4人 計4人 2023年 男性3人 女性4人 計7人 2022年 男性6人 女性4人 計10人 2021年 男性4人 女性2人 計6人 ※ 中途採用者比率 2024年:0% 2023年:0% 2022年:30% 2021年:50% |
|---|---|
| 主な採用実績校 |
■関東以北地区 早稲田大学、慶応大学、上智大学、東京大学、一橋大学、明治大学、法政大学、立教大学、中央大学、青山学院大学、学習院大学、筑波大学、東京外国語大学、お茶の水女子大学、横浜国立大学、静岡大学、北海学園大学、二松学舎大学 ■関西・中国地区 京都大学、同志社大学、立命館大学、関西学院大学、京都外国語大学、神戸大学、広島大学、岡山大学、神戸市外国語大学、名古屋市立大学、香川大学 ■九州地区 九州大学、北九州市立大学、鹿児島大学、熊本大学、長崎大学、佐賀大学、鹿屋体育大学、西南学院大学、福岡大学、鹿児島国際大学、志學館大学、琉球大学、福岡女子大学、鹿児島県立短大、鹿児島高専、久留米大学 |
| 過去の 作文テーマ |
2024年 「街づくり」
2023年 「投票率」 2022年 「道」 |
| 過去の 筆記試験 |
※解答に関するお問い合わせには、お答えできません |