

鹿児島県内の小学生がプログラミングのアイデアや技術を競う南日本小学生プログラミング大会(南日本新聞社主催、鹿児島信用金庫、南日本情報処理センター協賛)が2024年12月15日、鹿児島市の県医師会館ホールであった。プログラミング教育が小学校で必修化された2020年度に始まり、今回で5度目。優秀賞に選ばれた4~6年生10人が「みんなのみらい」をテーマに制作したゲームやアプリを発表した。最優秀賞に輝いた広木小5年の富田純白(ましろ)さんは、3月2日に東京で開かれる全国大会に鹿児島県代表として出場する。
2024年度全国選抜小学生プログラミング大会は3月2日(日)、東京・品川インターシティホールで開催されます。都道府県代表のプレゼンテーションは公式サイト(https://zsjk.jp/)内の特設コーナーでライブ配信します。
 最優秀賞
最優秀賞
Hands Talk ~ハンズトーク~
鹿児島市広木小5年

3年生の時、テレビドラマで知った手話に興味を持ち、手話技能検定5級の資格を持つ。「プログラムを通じて手話を広めたい」と学習アプリ制作を思い立った。キーボードをクリックすると対応する指文字が表れるようにしたり、よく使う単語をアニメで表現したりするなど工夫した。指文字の写真86枚を撮影し、キーボードにひも付けするのに手間がかかり、制作に4カ月を要したという。プログラムを使うことで身近な課題解決につなげたことや、「手話を広めたい」という思いにあふれる点などが評価された。「名前を呼ばれた時、『本当に(全国大会の出場権を)取れたの?』と信じられなかった」と戸惑いを隠せない。
3年生の時、プログラマーの母・貴子さん(46)の影響でプログラミングに興味を持った。絵を描くのが好きで、将来の夢は漫画家。全国大会に向けて「優勝を目指して頑張るとともに、広く手話を知ってもらう機会にしたい」と抱負を述べた。
 特別賞 鹿児島信用金庫賞
特別賞 鹿児島信用金庫賞
点字の世界へようこそ!
鹿児島市池田学園池田小6年(IT Kids LaB)

国語の教科書で読んだ「星空を届けたい」で知った点字を「多くの人に知ってもらいたい」と、文字を入力すると点字が表れるプログラムを作成。昨年度の優秀賞に続き、2年連続の入賞を果たした。子音と母音の組み合わせという点字の規則性に基づき、点を表示するのにペン拡張機能を使ったが「思う座標に点を打てず、試行錯誤の連続だった」と振り返る。
作品には「誰もが同じように暮らせる世界になってほしい」との思いを込めた。将来の夢は、ドラえもんのようなお助けプログラマー。「今回の作品は、そんな自分の未来への第一歩」と前を向いた。
 特別賞 南日本情報処理センター賞
特別賞 南日本情報処理センター賞
来たれ吹奏楽部!
トランペットを吹ききれ!
薩摩川内市隈之城小6年
(がらっぱ堂 ロボテク・ラボ)

金管バンドでトランペットを担当。遊びながら吹奏楽の楽しさを知ってもらおうと、音階練習などを取り入れたゲームアプリを開発した。トランペットの指遣いに合わせてキーを押すと音が鳴る仕組みで、同じ指遣いで吹き方を変えて演奏する音階は同時に他のキーを押すようにした。自分にまつわる課題をプログラミングで解決しようとした点などが評価された。
1年生の時、プログラマーの父・宏二さん(43)に憧れてプログラミングを始めた。将来の夢は世界中を旅すること。「プログラムも音楽も世界共通。どちらも頑張りたい」と意欲を見せた。
学校でのプログラミング教育が始まって5年目を迎え、応募される作品が少しずつ変わってきていることを感じました。最終審査にノミネートされた優秀賞10作品は、豊かな発想力と、すてきな表現力、高い技術力を感じられるものでした。「『みんなのみらい』が明るく、楽しく、便利になれば」という思いをこめて制作している姿が目に浮かぶ素晴らしい作品ばかりでした。使う人が笑顔になる様子を想像しながら、修正を繰り返し、工夫しながら根気強くプログラミングすることは大変な作業だったと思います。
みなさんが活躍する「未来」は、人工知能(AI)やロボットとともに生活するような今とはまったく違う世界になることが予想されます。毎日の生活の中で「あれ?」「ちょっと不便だな」と感じることに目を向ける“発想力”、アイデアを形にするための“表現力”や“技術”を身に付けることも大切です。誰のために作るのか、作品を通して一番伝えたいことは何かについて友達や家族、先生方と語らいながら、来年度の大会にすてきな作品を応募してください。

課長
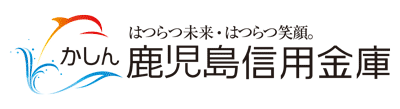



















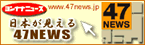
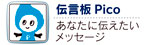
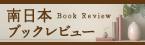
■プログラミングって何?
コンピューターにやってほしいことを、コンピューターが分かる言語で組み立てること。暮らしの中で使うスマートフォン、タブレット、パソコン、テレビゲームなどは、プログラミングによって動いている。プログラミングに必要とされる論理的な思考力や表現力を教育に取り込むため、プログラミング教育が2020年度から小学校で必修化された。