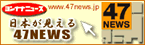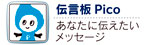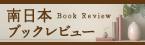AIセキュリティの社会実装を加速するパートナー戦略。ChillStackと大手企業・官公庁が「共創」する理由

株式会社ChillStackは、AIセキュリティ技術を活用した不正検知システムを開発する従業員30人規模のスタートアップです。一般的には、小規模なスタートアップが大手企業と対等なビジネスパートナーシップを築くことは容易ではありません。しかし、「楽楽精算」を提供する株式会社ラクスや、通信大手のKDDIグループのセキュリティ会社であるKDDIデジタルセキュリティ株式会社、SI大手のN株式会社、株式会社電通総研といった業界大手との戦略的提携を次々と実現しています。こうした大企業との協業を可能にしているのは、どのような戦略なのでしょうか。事業開発部を統率する中道にインタビューしました。
<プロフィール>
取締役 COO 中道 浩之
医療系メーカー商社にて、新規部門の立ち上げ〜BtoB営業・マーケティングまで幅広い領域で事業グロースに貢献。海外事業部門の立ち上げ〜欧米中に跨る社内プロジェクトなども指揮し、グローバルビジネスにも強み有り。その後、総合系ファームおよびプロフェッショナルファームにて、海外AIスタートアップと大手企業とのPoCや全社中計の策定、事業再生など幅広いプロジェクトを歴任。ChillStackへジョイン後は、強みを活かして主にBiz-Devを牽引。
大企業への導入障壁を打破するにはパートナー企業との連携が不可欠
──まず、ChillStackのパートナー戦略について、簡単に教えてください。
中道:ChillStackは「安全安心な環境を企業に提供し、皆さんが本業に集中できる環境を作る」ことを目指して、BtoB領域に特化した事業を展開しています。それを支えているのが、最先端のAIセキュリティ技術です。しかし、いくら優れた技術があっても、それだけでは市場に浸透させることは困難です。
とくに大企業はセキュリティ要件が非常に厳しく、新しいツールや技術の導入には長期間の検証が必要です。全社での公平性を保つ必要があるため、一部門だけでの先行導入は困難ですし、ほかにも既存システムとの連携、膨大なデータ移行、従業員への教育コストなど、導入時のハードルが多数存在します。
また、最新トレンドの採用にも慎重で、いまだにChatGPTを導入していない企業もたくさんあります。ブラウザもMicrosoft Edgeに限定されるなど制約が多いのも実情です。
こうした大企業こそChillStackの技術が貢献できると考えていますが、とはいえ小規模のスタートアップが単独で大企業の複雑な要件に対応するのは限界がありますし、そもそも相手にしてもらえることさえ少ないというのが実情です。そこで、大企業にしっかりと入り込んでいる別サービス企業(SI、コンサルティングファーム、ITベンダー)と関係構築を行いました。彼らは彼らで自分たちのソリューションやサービス単体ではお客様の課題を解決しきれず困っており、うまくパズルのピースとしてハマるようなビジネス形態や座組を提案しながら、根気よく関係性を構築しています。

──そのパートナーシップの形態について教えてください。
中道:大きく2つの形態があります。ひとつはOEM形態で、大手企業のブランドのもとでChillStackの技術のみを提供するケース。もうひとつは、両社のブランドを並べて展開するダブルネームでの戦略的提携です。
ChillStackは高い技術力を有している一方で、スタートアップとして規模が小さく、十分と言えるほどのブランド認知を得られていません。そのため、ChillStackの信頼性を高められる後者のダブルネーム戦略を重視しています。
──大企業が直面する課題の中で、ChillStackが特に注力している分野はどこですか。
中道:今いちばん伸びているのは経費精算の不正検知です。経費精算システム自体は成熟したマーケットになっていて、多くのベンダーがサービスを提供しています。ただ、お客様には経費精算システム外での不正や間違いを防止したいニーズがあるのに、既存システムでは実現できていないんです。
この経費精算の不正検知というのは、まさにスタートアップが狙うべき「ちょうどいいマーケット」なんです。ニッチだが一定の需要がある。大きすぎると大手が入ってきますし、小さすぎると商売になりませんから、この絶妙な規模のマーケットを見つけることが重要です。
大手企業や官公庁との協業を通じて高まる社会的信頼と実装力
──では、次に具体的な協業事例について教えてください。
中道:ラクス社とは、不正経費自動検知クラウド「Stena Expense」のリリース当初から現場レベルでは共同提案などの活動を続けてきて、2025年に戦略的パートナーとして契約関係を持った会社対会社でのお付き合いを正式に開始しました。
現場では大手企業への提案依頼書(RFP)に際し、ラクス社とともに共同で実施しています。昨今のトレンドとしては、単なる経費処理の効率化だけでなく「不正や間違いを防止する機能」も要件として明記されていることも少なくなく、ラクス社の「楽楽精算」だけでは、どうしても「運用ルールで対応します」といった提案にとどまってしまうんです。そのためAIによる不正検知というChillStackの技術も組み合わせることで、経費精算の効率化と不正検知の両方を技術的に実現できる包括的な提案ができ、結果的にコンペで採用されたケースもあります。
別事業では、KDDIデジタルセキュリティ社とのOEM提携も進んでいます。IoT機器の脆弱性診断から報告書作成までの技術的な側面を全てChillStackが担当する「IoTセキュリティ診断サービス」を、KDDIデジタルセキュリティ社がサービスとして展開しています。大手通信会社グループと技術連携できた良い事例です。
さらに、官公庁や公共向け領域への展開も進めており、大手SI企業との連携を通じて地方自治体の案件で落札に至った実績があります。その後の本格導入交渉にもつながっており、ChillStackの技術は行政セクターにおいても高く評価されています。
確実な成果とスピード対応で築く大手企業との信頼関係
──ずばり、パートナー企業がChillStackを選ぶ理由は何でしょうか。
中道:理由は3つあると考えています。ひとつは多種多様な大手企業とのパートナー契約実績がある点です。「Stena Expense」の導入実績に加え、他社と協業ができているということは他のパートナー企業に安心感を与えます。
2つ目が「本当にできるの?」と言われたときに、確実にできると答えられるだけのスピード感と実現力(技術力)があること。3つ目は、提携パートナー様の現場メンバー同士のフィーリングが合うことでしょうか。
特に3つ目については、仕事を依頼されたときに誠実かつスピーディに対応するという基本姿勢はもちろんですが、それ以上にコミュニケーションの相性が重要です。例えば、パートナー企業の方からよく「お疲れさまです」という挨拶で電話をいただくのですが、同じ会社の仲間のような距離感の近さを感じます。パートナー企業の上層部から現場メンバーまで幅広くコミュニケーションをとりながら密接な協力関係が築けることも大きいのではないかと感じます。
──2つ目に挙げられていた「スピード感」について、何か具体例はありますか?
中道:ある地方自治体では、職員の経費申請における交通費の妥当性を自動で検証したいという課題がありました。ChillStackの開発メンバーに相談したところ、外部のAPIやAIロジックを使って約1週間でデモ機能を作成し、迅速に先方へ「できます」と回答できました。課題の相談から具体的な解決策の提示までを1〜2週間で対応できるスピード感は、間に入るパートナー企業にとっても心強いのではないかと感じています。
──パートナー戦略を進めるうえで、転機となった出来事はありますか。
中道:シリーズAの資金調達がブレイクスルーのタイミングでした。対外的に一定の信用度ができ、大手ファンドからも出資をいただいたことで複数のパートナー企業との連携スピードも早まりました。パートナー企業数が増えるほどに信頼性も高まり、その後も複数の大手企業からの戦略的パートナーシップの引き合いがくるなど良い軌道に乗っています。
今後はChillStackの強みを生かした協業体制を強化し、パートナー企業にもChillStackのソリューションを軸としたより多くの提案をしていただけるようにすることが大切だと感じています。
パートナー戦略を支えるオープンな体制
 ──社内の体制についても教えてください。パートナー連携を成功させるために、どのような文化を築かれていますか。
──社内の体制についても教えてください。パートナー連携を成功させるために、どのような文化を築かれていますか。
中道:良くも悪くも「自社単独でやりきる」という考え方に固執しないような会話や考え方を意識しています。ビジネスの複雑性の増大に伴い、お客様の課題も一筋縄ではいかない状況になっており、そのトレンドは今後も増していくと感じているからです。パートナー企業が抱える課題、その先にいるエンドユーザーが抱える課題をオープンに議論し、どのような座組やサービス提供の形がWin-Winにつながるかを、現場のメンバーそれぞれの視点で意識してほしいと考えています。
また、ビジネス部門だけでは捕捉しきれない技術的なネタや情報をエンジニアから共有してくれるような環境であることも非常に良いと思っています。技術者目線でのネタは、お客様やパートナー企業と話す時にも非常に役立ちます。このような相互での情報共有文化や他社と協業することを念頭においたオープンな雰囲気は、メンバー全員の感度にも良い影響を与えます。また、パートナー企業との勉強会があるときは積極的にエンジニアメンバーも連れて行くことで彼らにも刺激を得てもらいつつ、パートナー企業との連携を肌で感じてもらう工夫もしています。技術的なことは、私よりエンジニアが答えたほうが説得力もありますしね。
──パートナー企業との連携により、エンジニアが得られる経験やメリットもあるのでしょうか。
中道:パートナー企業とともにお客様の現場を訪れ、実情を知ることは、ものづくりにおいて非常に重要です。エンタープライズ企業の現場の実態や困りごとを自分の目で見て耳で聞くということは、ドメイン知識の深掘りに有用ですし、お客様の顔が見える場所に行けるのは刺激になっているとフィードバックをもらっています。
また、ラクス社と共催した技術勉強会は、お互いを知るためにも有効でした。超大手が使うシステムを手がける同社のエンジニアとの交流は、裏側に使われている技術やプロダクトの作り方、考え方の学習になり、これまでとは異なる視点を得られる貴重な機会になったはずです。
自信のあるプロダクトを日本中に広げたい
──今後、開拓したい潜在層はありますか。
中道:引き続きSI企業やITベンダーとの裾野を広げつつ、監査という領域では税理士法人や監査系の企業、いわゆる監査法人の企業とお取り組みをしたいと考えています。
──最後に、ChillStackが目指すパートナーネットワークの将来像を聞かせてください。
中道:ERPで高いシェアを持つSAPのような広範囲のパートナーネットワークが築ける流通網に昇華させたいと思っています。SAPは日本に100社以上のパートナー企業がいて、大手SIからコンサルティングファーム、中堅SIまで、ありとあらゆるところに入り込み、パートナー企業経由でソリューションを提供しています。クラウド型CRMで世界最大手の「Salesforce(セールスフォース)」も同様です。
こうしたことからみても、やはりパートナー戦略こそがBtoBビジネス成功の鍵だと考えています。BtoCビジネスであれば、自社完結でサービスを提供するのもひとつの戦略です。しかし、中堅以上の企業を相手にするBtoBビジネスでは、複雑な要求に応えるためにもパートナー企業との共創は不可欠です。
パートナー企業を増やし、Win-Winの関係性を築くことで、自信を持って開発したプロダクトを日本中に広げる——それが企業の安心・安全な環境づくりを支え、皆さんが本業に集中できる社会につながると考えています。
▼ChillStack HP
▼採用ページ
現在ChillStackでは一緒に働く仲間を絶賛募集中です。
少しでも興味のある方は是非カジュアル面談にご応募ください。
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ