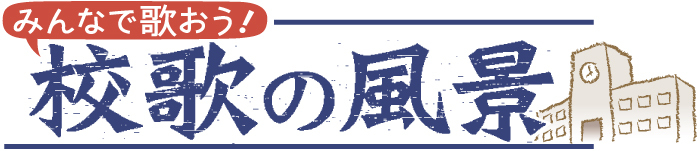校庭から蒲生八幡神社の大木(左奥)が見える蒲生小学校=姶良市
今年は蒲生八幡神社の創建900年の節目に当たる。学校から道一本隔てた境内にあるクスノキは、校歌に歌われる通り〈日本一の楠〔くす〕〉だ。樹齢は推定1500年といわれ、目通りの幹回りは24.22メートル。樹種を問わず、日本一の巨樹と認定されている。蒲生小の児童はみな、この大クスに見守られて育った。
学校の正面に広がるのが蒲生城跡。戦国武将の島津義弘は関ケ原合戦で敵中突破し、帖佐(姶良市)に戻った。そして徳川勢を迎え撃とうとしたのが、難攻不落の「竜ケ城〔りゅうがじょう〕」と呼ばれたこの城だった。今では公園が整備され、卒業・入学式のころは〈龍〔りゅう〕が丘の桜花〔さくらばな〕〉が山肌を薄桃色に染める。
校歌には、〈希望の鐘〉〈理想の旗〉〈文化の花〉と無限の可能性を秘めた児童の未来を思わせるフレーズが並ぶ。校歌制定は太平洋戦争終戦から遠くない1950(昭和25)年11月。作詞した別當〔べっとう〕法道〔のりみち〕さん(97)=姶良市豊留=は「戦争が終わり、時代が変わった。平和や自由への思いを入れたかった」。〈自由の光満ち満ちて〉生まれた校歌だった。作曲は鹿児島大学教授だった林幸光さん。
別當さんは当時、蒲生小の教諭。50年2月には蒲生中学校の校歌を作詞した。「一般公募にペンネームで応募したが、採用されるとは夢にも思わなかった」。小学校校歌も名を伏せ応募し一等に選ばれた。「70年以上歌い継がれ光栄の至り」と目を細める。
才田修〔おさむ〕校長(51)は「校歌に歌われた歴史と自然は蒲生小の魅力。これからも守り続けたい」と話した。
●メモ 児童の声が〈緑の山にこだま〉するほど、自然との距離が近い。四季の変化も感じられ、全校で俳句学習に取り組む。かわなべ青の俳句大会では13年連続の学校賞を受ける。地域住民との結び付きも強く、ボランティア団体「蒲生郷おかべ会」の森林環境体験学習は、毎年の恒例行事となっている。
(南日本新聞2023年3月20日付)