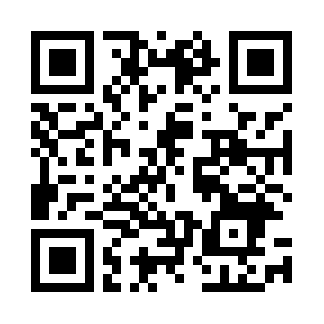第11部

議会制度導入
「公議輿論」目指し模索
明治2(1869)年3月7日、東京・神田橋門内の旧姫路藩邸に、諸藩から選ばれた代表者(公議人)ら227人が集まった。「心を公平に存し議を精確に期し」との詔書が示され、明治政府の議事機関「公議所」が開設された。
政府は「五箇条の御誓文」で掲げた「公議輿論(よろん)」の実現を模索していた。明治元年、議会制度の調査機関として「議事体裁取調所」を置き、組織づくりに着手し、翌年2月には詔書で公議所の設置を布告した。
欧米の立憲制や議会制は、幕末に有識者や留学生らによって持ち込まれていた。翻訳書や新聞、演説会など、知識人から市井の人々にも浸透していった。
公議所の議場は欧米に似た形式で、公議人は抽選で決められた席に着いた。藩主が推挙した“官選”による議院だったが、森有礼の「廃刀案」など開明的な議案をはじめ、6月までに66議案が提出された。開設当時の新聞には「庶民に、政府を扶(たす)け、公明正大の政を施し行うべきの権を許されたり」「開化文明の一大改革」(横浜新報もしほ草)と評された。
大きな期待を持って迎えられ、その後、集議院と改められた。しかし、集議院は明治3年には開かれなくなってしまった。政府が審議内容を採用しないなど十分な成果を上げられず、在京費用がかさむと代表者を派遣しない藩主もいた。理想とかけ離れた実情で、失敗に終わってしまった。
政府は「五箇条の御誓文」で掲げた「公議輿論(よろん)」の実現を模索していた。明治元年、議会制度の調査機関として「議事体裁取調所」を置き、組織づくりに着手し、翌年2月には詔書で公議所の設置を布告した。
欧米の立憲制や議会制は、幕末に有識者や留学生らによって持ち込まれていた。翻訳書や新聞、演説会など、知識人から市井の人々にも浸透していった。
公議所の議場は欧米に似た形式で、公議人は抽選で決められた席に着いた。藩主が推挙した“官選”による議院だったが、森有礼の「廃刀案」など開明的な議案をはじめ、6月までに66議案が提出された。開設当時の新聞には「庶民に、政府を扶(たす)け、公明正大の政を施し行うべきの権を許されたり」「開化文明の一大改革」(横浜新報もしほ草)と評された。
大きな期待を持って迎えられ、その後、集議院と改められた。しかし、集議院は明治3年には開かれなくなってしまった。政府が審議内容を採用しないなど十分な成果を上げられず、在京費用がかさむと代表者を派遣しない藩主もいた。理想とかけ離れた実情で、失敗に終わってしまった。
□ ■ □
明治5年4月、政府の立法諮問機関の役割を果たしていた「左院」の宮島誠一郎(米沢藩出身)が、憲法制定と国会開設を説いた「立国憲議」を提出した。前年の廃藩置県で統治体制が大きく変わる中での出来事だった。
宮島は「日本の人民は長年の君主独裁で権利と義務を正しく知らずに混乱が起きている」と指摘。まず憲法を制定し、民法、刑法を制定するとした。各省の長官と次官による「右院」と府県官員による会議を当面の「民撰(みんせん)議院」とする構想だった。そして開化と共に“真”の民撰議院を設けることが好ましいとした。
だが、宮島の建議は左院議長の後藤象二郎によって却下された。「憲法は人民が関わって決めるべき」とする副議長・江藤新平の反対を受けたとされる。
その後、江藤が司法卿に転ずると、左院内では欧米式の上下院の設置構想が練られるなど、議会開設に向けた議論が進んだ。同年8月の「国会議院手続取調」では、国会の東京設置、90日以内とする会期日数、資産のある農工商による選挙で議員を決める―など具体的な方針もあった。
だが左院の進めた構想が実現することはなかった。大きな障壁になったのは、政府内部で政治問題として持ち上がっていた征韓論争だ。宮島は「手続取調」の扱いについて、後年「民撰議院設立建白書」を提出する板垣退助にも相談したが、積極的な動きはなかった。
宮島は「日本の人民は長年の君主独裁で権利と義務を正しく知らずに混乱が起きている」と指摘。まず憲法を制定し、民法、刑法を制定するとした。各省の長官と次官による「右院」と府県官員による会議を当面の「民撰(みんせん)議院」とする構想だった。そして開化と共に“真”の民撰議院を設けることが好ましいとした。
だが、宮島の建議は左院議長の後藤象二郎によって却下された。「憲法は人民が関わって決めるべき」とする副議長・江藤新平の反対を受けたとされる。
その後、江藤が司法卿に転ずると、左院内では欧米式の上下院の設置構想が練られるなど、議会開設に向けた議論が進んだ。同年8月の「国会議院手続取調」では、国会の東京設置、90日以内とする会期日数、資産のある農工商による選挙で議員を決める―など具体的な方針もあった。
だが左院の進めた構想が実現することはなかった。大きな障壁になったのは、政府内部で政治問題として持ち上がっていた征韓論争だ。宮島は「手続取調」の扱いについて、後年「民撰議院設立建白書」を提出する板垣退助にも相談したが、積極的な動きはなかった。
□ ■ □
熱を帯びた征韓論争の末、「明治6年政変」で西郷隆盛や板垣、江藤らが下野すると、直後の同年11月、政府の実権を握る立場となった大久保利通は、「立憲政体に関する意見書」を示した。
岩倉使節団の欧米視察を経験した大久保は、日本にふさわしい政体を「君民共治」(立憲君主制)と説いた。一方、フランスの民主政治を「凶暴残虐は君主専制より甚だしい」とも評した。
憲法については「君民共治のために必要で、上は君権を定め、下も民権を限る」と評価。制定は欧州各国の模倣ではなく、日本の国風や人情、時勢などに配慮するべきだとした。三権分立の重要性を説いていたが、議会については「民選」を想定していなかった。
この意見書が出されたのは、板垣らが「民撰議院設立建白書」を提出する2カ月ほど前のこと。伊藤博文は「大久保公は早くより立憲政体を主唱された有力な一人である」と回想した。
慶応大学の小川原正道教授は「急進的か、段階的かなど考え方の違いはあったが、大久保ら政府中枢も国会や憲法の必要性は共通した認識だった」と語る。
岩倉使節団の欧米視察を経験した大久保は、日本にふさわしい政体を「君民共治」(立憲君主制)と説いた。一方、フランスの民主政治を「凶暴残虐は君主専制より甚だしい」とも評した。
憲法については「君民共治のために必要で、上は君権を定め、下も民権を限る」と評価。制定は欧州各国の模倣ではなく、日本の国風や人情、時勢などに配慮するべきだとした。三権分立の重要性を説いていたが、議会については「民選」を想定していなかった。
この意見書が出されたのは、板垣らが「民撰議院設立建白書」を提出する2カ月ほど前のこと。伊藤博文は「大久保公は早くより立憲政体を主唱された有力な一人である」と回想した。
慶応大学の小川原正道教授は「急進的か、段階的かなど考え方の違いはあったが、大久保ら政府中枢も国会や憲法の必要性は共通した認識だった」と語る。