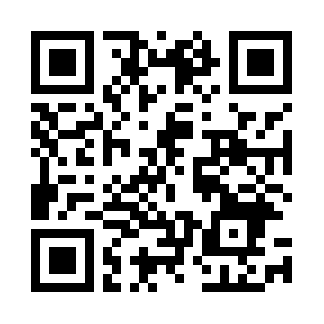第4部

鉄道開業
交通網整備 発展の柱に
秋晴れの下、ひときわ甲高い汽笛が一声響いた。車輪がゆっくりとレールの上を回り始め、明治天皇を乗せた蒸気機関車は新橋を目指して動き出した。
明治5(1872)年9月12日午前、新橋―横浜間(29キロ)の鉄道開業式が横浜駅で盛大に催された。日の丸をはじめ万国の国旗が翻る会場には紅白の提灯(ちょうちん)も飾られ、日本初の鉄道開通は国家的イベントとなった。
天皇は直衣(のうし)に烏帽子(えぼし)姿で臨席した。皇族や各国公使に加え、岩倉使節団として外遊中の面々を除く、三条実美や西郷隆盛ら政府要職も顔をそろえ、国の威信をかけた事業だった。
天皇は「交通輸送が便利になることで交易が活性化し、庶民生活が豊かになることを期待する」と勅語を発した。蒸気車は正午に出発し、午後1時に新橋駅に到着。天皇はそのまま新橋駅での開場式にも臨み記念日を祝った。
明治5(1872)年9月12日午前、新橋―横浜間(29キロ)の鉄道開業式が横浜駅で盛大に催された。日の丸をはじめ万国の国旗が翻る会場には紅白の提灯(ちょうちん)も飾られ、日本初の鉄道開通は国家的イベントとなった。
天皇は直衣(のうし)に烏帽子(えぼし)姿で臨席した。皇族や各国公使に加え、岩倉使節団として外遊中の面々を除く、三条実美や西郷隆盛ら政府要職も顔をそろえ、国の威信をかけた事業だった。
天皇は「交通輸送が便利になることで交易が活性化し、庶民生活が豊かになることを期待する」と勅語を発した。蒸気車は正午に出発し、午後1時に新橋駅に到着。天皇はそのまま新橋駅での開場式にも臨み記念日を祝った。
□ ■ □
蒸気の力で陸上を疾走する蒸気車は、まさに産業革命の産物で、文明国の象徴だった。“最初の工業国家”イギリスで1830年に運行が始まって以来、基幹の交通輸送インフラは瞬く間に世界各地に広まった。
幕末の薩摩藩英国留学生の面々は初乗車体験に、「早きこと疾風の如し」(松村淳蔵)「気車の進行速やか」(畠山義成)と一様に驚いた。また、慶応3(1867)年に渡欧し、後に経済界の重鎮となった渋沢栄一も「国家はかかる交通機関を持たねば発展はしないと思った」と回顧していた。
“開港”以来、幕府にはフランスやアメリカが、日本国内での鉄道敷設をたびたび提案していた。明治政府にも同様だったが、鉄道の経営権を外国側が持つ「外国管轄方式」の建言がほとんどだった。政府は“独立”が脅かされる危険性を危惧し、踏み切れずにいた。
だが、殖産興業の推進に鉄道の必要性は認識しており、明治2年2月までに「我(わが)内国人民合力を以(もっ)て」敷設すると決めた。軍備充実を主張する西郷や黒田清隆らは反対したが「長州五傑」の井上勝が鉄道頭(てつどうのかみ)として事業を推進。英国人技師エドモンド・モレルの下で明治5年5月に品川―横浜間を仮開業、9月に天皇臨席の開業式にこぎ着けた。
新橋―横浜間は9月13日から営業開始。旅客車が1日9往復運行し、所要時間は53分(徒歩は約6時間)。途中駅は品川、川崎、鶴見、神奈川だった。新橋―横浜間の運賃は1円12銭5厘~37銭5厘。白米が10キロ約35銭の時代で、手軽な乗り物ではなかった。
幕末の薩摩藩英国留学生の面々は初乗車体験に、「早きこと疾風の如し」(松村淳蔵)「気車の進行速やか」(畠山義成)と一様に驚いた。また、慶応3(1867)年に渡欧し、後に経済界の重鎮となった渋沢栄一も「国家はかかる交通機関を持たねば発展はしないと思った」と回顧していた。
“開港”以来、幕府にはフランスやアメリカが、日本国内での鉄道敷設をたびたび提案していた。明治政府にも同様だったが、鉄道の経営権を外国側が持つ「外国管轄方式」の建言がほとんどだった。政府は“独立”が脅かされる危険性を危惧し、踏み切れずにいた。
だが、殖産興業の推進に鉄道の必要性は認識しており、明治2年2月までに「我(わが)内国人民合力を以(もっ)て」敷設すると決めた。軍備充実を主張する西郷や黒田清隆らは反対したが「長州五傑」の井上勝が鉄道頭(てつどうのかみ)として事業を推進。英国人技師エドモンド・モレルの下で明治5年5月に品川―横浜間を仮開業、9月に天皇臨席の開業式にこぎ着けた。
新橋―横浜間は9月13日から営業開始。旅客車が1日9往復運行し、所要時間は53分(徒歩は約6時間)。途中駅は品川、川崎、鶴見、神奈川だった。新橋―横浜間の運賃は1円12銭5厘~37銭5厘。白米が10キロ約35銭の時代で、手軽な乗り物ではなかった。
□ ■ □
政府は新橋―横浜間の敷設を端緒に鉄道網を各地に延ばしていく。明治6年9月には同区間の貨物運行を始め、翌年5月に大阪―神戸、明治10年に京都―神戸が開業。目的は人の輸送にとどまらず、各物産の生産地と消費地、輸出地(港)を結束することだった。
沿線では養蚕や織物業をはじめ各産業が興り、鉱山からの産出物輸送などのため、鉄道網はさらに張り巡らされていった。収益が見込めると明治10年代には最初の民間鉄道会社「日本鉄道」が設立(明治14年)。企業勃興(ぼっこう)の一助にもなった。
鉄道敷設は人々の生活にも影響を及ぼした。ごう音を上げ、見たことのない速さで陸を駆け抜ける蒸気車は「陸(おか)蒸気」ともてはやされ、乗客には羨望(せんぼう)のまなざしが向けられた。
運賃は割高だったが、鉄道を使った各地への旅行など観光業の端緒にもなった。またダイヤの設定により、全国一律の時間運行が求められるようになったため、地域で時刻が異なる「不定時法」から、明治6年1月1日から導入された西洋式の「定時法」定着にも一役買った。
跡見学園女子大学の老川慶喜教授(68)=日本経済史=は「各種の殖産興業を支えたのが鉄道敷設で、明治政府にとってインフラ整備も重要な施策の一つだった」と指摘した。
沿線では養蚕や織物業をはじめ各産業が興り、鉱山からの産出物輸送などのため、鉄道網はさらに張り巡らされていった。収益が見込めると明治10年代には最初の民間鉄道会社「日本鉄道」が設立(明治14年)。企業勃興(ぼっこう)の一助にもなった。
鉄道敷設は人々の生活にも影響を及ぼした。ごう音を上げ、見たことのない速さで陸を駆け抜ける蒸気車は「陸(おか)蒸気」ともてはやされ、乗客には羨望(せんぼう)のまなざしが向けられた。
運賃は割高だったが、鉄道を使った各地への旅行など観光業の端緒にもなった。またダイヤの設定により、全国一律の時間運行が求められるようになったため、地域で時刻が異なる「不定時法」から、明治6年1月1日から導入された西洋式の「定時法」定着にも一役買った。
跡見学園女子大学の老川慶喜教授(68)=日本経済史=は「各種の殖産興業を支えたのが鉄道敷設で、明治政府にとってインフラ整備も重要な施策の一つだった」と指摘した。