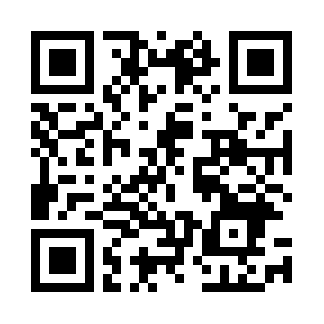第5部

西洋料理
牛鍋が流行 政府も奨励
「牛は至極高味(こうみ)(おいしい)でごすネ」「文明開化といッてひらけてきやしたから、我々(われわれ)までが食うようになったのは実にありがたいわけでごス」―。
戯作(げさく)者仮名垣魯文(かながきろぶん)の書いた「安愚楽(あぐら)鍋」は、文人画家、花魁(おいらん)、落語家などさまざまな階層の客があぐらをかきながら、牛鍋を囲む庶民の生態を素描した。明治4~5(1871~72)年に書かれ、牛肉のおいしさと効用などを訴える文明礼賛の書として支持された。
牛鍋は牛肉とネギを、みそやしょうゆ、砂糖で煮込んだ料理だ。流行は瞬く間だった。安政5(1858)年、アメリカなど諸外国と通商条約が結ばれたのを皮切りに、外国人の居留地向けに牛肉の需要が増加した。「おいしい」と分かれば横浜、東京などで牛肉店や牛鍋屋が相次ぎ開店していった。牛をはじめ肉食が庶民に受け入れられる様子は外国人に風刺されたほど。英国人画家ワーグマンは「牛肉を食べ、ビールを飲めば人間になれると思っている」と、オウムに見立てた風刺画で当時の日本人の“西洋崇拝”を皮肉った。
明治期の風俗史に詳しい川崎市市民ミュージアム元学芸室長の湯本豪一さん(67)は「牛肉が広く受け入れられたのは日本的な調理法が大きかった。庶民の口にぴったり合った」と解説する。
戯作(げさく)者仮名垣魯文(かながきろぶん)の書いた「安愚楽(あぐら)鍋」は、文人画家、花魁(おいらん)、落語家などさまざまな階層の客があぐらをかきながら、牛鍋を囲む庶民の生態を素描した。明治4~5(1871~72)年に書かれ、牛肉のおいしさと効用などを訴える文明礼賛の書として支持された。
牛鍋は牛肉とネギを、みそやしょうゆ、砂糖で煮込んだ料理だ。流行は瞬く間だった。安政5(1858)年、アメリカなど諸外国と通商条約が結ばれたのを皮切りに、外国人の居留地向けに牛肉の需要が増加した。「おいしい」と分かれば横浜、東京などで牛肉店や牛鍋屋が相次ぎ開店していった。牛をはじめ肉食が庶民に受け入れられる様子は外国人に風刺されたほど。英国人画家ワーグマンは「牛肉を食べ、ビールを飲めば人間になれると思っている」と、オウムに見立てた風刺画で当時の日本人の“西洋崇拝”を皮肉った。
明治期の風俗史に詳しい川崎市市民ミュージアム元学芸室長の湯本豪一さん(67)は「牛肉が広く受け入れられたのは日本的な調理法が大きかった。庶民の口にぴったり合った」と解説する。
□ ■ □
獣肉食は江戸幕府が禁令を出し、仏教の「殺生禁断」や神道のけがれの意識の影響も相まって禁忌とされていた。例外だったのは薩摩藩。幕末、徳川慶喜から豚を再三所望された家老小松帯刀が、国元に「皆々差上候(さしあげそうろう)(全部差し上げた)」と書いた手紙が残るなど、薩摩では豚肉を食べる習慣が根付いていた。中国から、実質支配していた琉球を通じて入ってきた可能性が高いとみられている。だが、これを除くと一般的には薬用などで食べられる程度だった。
禁忌が薄れていったのは、政府が肉食を奨励したという背景があった。西洋列強国に認められるには肉食を解禁し、生活の洋式化を進めることが必要だった。欧米人との体格差解消も念頭にあった。
明治5年1月、明治天皇は初めて西洋料理と肉食を体験、大久保利通に「外国人との交際に必要だから食べた」との旨を語った。外国要人と食する宮中の正式料理は西洋料理だ。天皇は和服と和食を好んだとされるが、西洋流のテーブルマナーに取り組んだ。
知識人も洋食や肉食導入に一役買った。福沢諭吉は、けがれ意識からみだりに肉食を嫌う風潮を「道理をわきまえない」と切り捨て、いち早くナイフやフォークといった道具や食べ方を教える絵入りの「西洋衣食住」を出した。仮名垣や福沢に影響された加藤祐一らの指南本が次々に続いた。
禁忌が薄れていったのは、政府が肉食を奨励したという背景があった。西洋列強国に認められるには肉食を解禁し、生活の洋式化を進めることが必要だった。欧米人との体格差解消も念頭にあった。
明治5年1月、明治天皇は初めて西洋料理と肉食を体験、大久保利通に「外国人との交際に必要だから食べた」との旨を語った。外国要人と食する宮中の正式料理は西洋料理だ。天皇は和服と和食を好んだとされるが、西洋流のテーブルマナーに取り組んだ。
知識人も洋食や肉食導入に一役買った。福沢諭吉は、けがれ意識からみだりに肉食を嫌う風潮を「道理をわきまえない」と切り捨て、いち早くナイフやフォークといった道具や食べ方を教える絵入りの「西洋衣食住」を出した。仮名垣や福沢に影響された加藤祐一らの指南本が次々に続いた。
□ ■ □
西洋の主食パンを売る店も広まり始めた。中でも和洋折衷の発明は「あんパン」。東京で創業した木村屋総本店が、パン生地であんこを包み人気を博した。侍従の山岡鉄舟(元幕臣)が天皇にも献上し、明治8年御用達になった。
本格的な西洋料理店は東京・築地采女町の「精養軒」をはじめ、麹町、上野など明治5年ごろまでにいくつも開業していた。しかし、政府要人や上流階級向けで一般人には縁遠い存在だった。東京、大阪、京都など都市部から手頃な洋食屋が地方へ展開するのは、明治も10年代になってからだ。
鹿児島では15年に「城南松原亭ニ於(おい)テ洋食ノ饗応(きょうおう)アリ」との記述があった(前坊洋著「明治西洋料理起源」)。鹿児島の社会風俗に詳しい唐鎌祐祥氏の著書によると10年ごろ、鹿児島市の大門口に「ちょっとした洋食」が食べられる万勝亭、青柳亭、松原亭、朝日楼などの料亭が軒を並べた。
国士館大21世紀アジア学部教授の原田信男さん(68)=日本生活文化史=は「牛鍋は日本料理の伝統を引く新しい和食と言っていい。しかし、庶民の洋食への関心を高め、その普及を準備した」と評価する。
本格的な西洋料理店は東京・築地采女町の「精養軒」をはじめ、麹町、上野など明治5年ごろまでにいくつも開業していた。しかし、政府要人や上流階級向けで一般人には縁遠い存在だった。東京、大阪、京都など都市部から手頃な洋食屋が地方へ展開するのは、明治も10年代になってからだ。
鹿児島では15年に「城南松原亭ニ於(おい)テ洋食ノ饗応(きょうおう)アリ」との記述があった(前坊洋著「明治西洋料理起源」)。鹿児島の社会風俗に詳しい唐鎌祐祥氏の著書によると10年ごろ、鹿児島市の大門口に「ちょっとした洋食」が食べられる万勝亭、青柳亭、松原亭、朝日楼などの料亭が軒を並べた。
国士館大21世紀アジア学部教授の原田信男さん(68)=日本生活文化史=は「牛鍋は日本料理の伝統を引く新しい和食と言っていい。しかし、庶民の洋食への関心を高め、その普及を準備した」と評価する。