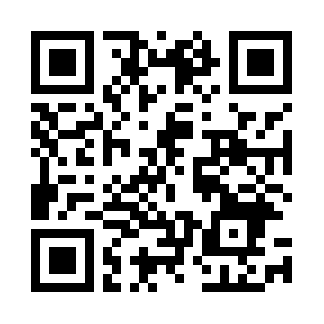第8部

市・町・村の発足
中央”支配”が順次確立
維新後、地方行政の混乱は小さくなかった。明治5(1872)年以降、地方行政の再編を目指して「大区・小区制」が導入された。江戸時代以来の町村複数を小区に編成してその上に大区を置き、それまで年貢徴収や治安維持を担った庄屋名主などが廃された。
政府は、幕藩体制下における生活共同体の基礎で自治色も強かった「町村」をなくそうと、政府に従属的な大区の区長、小区の戸長を官選で配置した。明治4年の廃藩置県まで、旧藩では独立財政を維持するなど地方の権限が強く、国と地方の統一的国家財政(中央集権)を目指す政府にとって、旧来の地方制度は“邪魔”な存在だった。
政府の思惑とは別に、各地の実情を考慮しない画一的な小区割りは、住民から反発を招いた。同時進行した地租改正と合わせて、度重なる地方改革に社会の不満は強まっていった。
「大区・小区制」の不評に危機感を持った政府は明治11年、地方制度の基礎となる三新法(郡区町村編制法、府県会規則、地方税規則)を制定した。従来の町村を復活させ、町・村の長は民選にして地方自治を一部認めた。一方、税規則については、地方からの税収配分を国に手厚くするなど集権化は維持された。
厳しい財政事情の地方では、政府の直轄事業や補助金制度による道路・河川の改修など公共インフラの整備も進み、次第に中央依存の体質が出来上がっていった。
政府は、幕藩体制下における生活共同体の基礎で自治色も強かった「町村」をなくそうと、政府に従属的な大区の区長、小区の戸長を官選で配置した。明治4年の廃藩置県まで、旧藩では独立財政を維持するなど地方の権限が強く、国と地方の統一的国家財政(中央集権)を目指す政府にとって、旧来の地方制度は“邪魔”な存在だった。
政府の思惑とは別に、各地の実情を考慮しない画一的な小区割りは、住民から反発を招いた。同時進行した地租改正と合わせて、度重なる地方改革に社会の不満は強まっていった。
「大区・小区制」の不評に危機感を持った政府は明治11年、地方制度の基礎となる三新法(郡区町村編制法、府県会規則、地方税規則)を制定した。従来の町村を復活させ、町・村の長は民選にして地方自治を一部認めた。一方、税規則については、地方からの税収配分を国に手厚くするなど集権化は維持された。
厳しい財政事情の地方では、政府の直轄事業や補助金制度による道路・河川の改修など公共インフラの整備も進み、次第に中央依存の体質が出来上がっていった。
□ ■ □
明治22(1889年)年7月10日、鹿児島県内各地の産業を紹介する「興業館」(現・県立博物館旧考古資料館)において盛大な式典が開かれた。4月に発足した、鹿児島市による仮市役所の開庁式で、当初の山之口馬場町からの引っ越しだった。
開庁式には市内各地の学校や寺院の関係者、近隣の村長ら名士が一堂に会し鹿児島市の門出を祝った。初代市長の上村行徴(ゆきあき)は「勤勉不撓(ふとう)の精神を以(もっ)て将来市民の幸福を増進」するとあいさつ。その上で「聖旨に報い奉り又閣下が懇諭に違(たが)うなき」を誓った。地方自治を喜び、市民への忠誠を宣言した。
明治政府の発足以降、たびたび地方の再編が繰り返されたが、この時発足した鹿児島市が現在に至る。あいさつの行間から「国の方から与えられ地方自治制度であることを看取することができる」(鹿児島市史II)と指摘され、各種権限は限定された自治体と言えた。鹿児島市は、鹿児島郡に属していた50町村をまとめた区域で発足(上町、西田など約14平方キロ)。当時の人口は4万7512人だった(鹿児島市史II)。
甲南大学名誉教授の高寄昇三さん(84)=地方財政=は「明治期の地方史は中央の『支配』が確立していった過程」とみる。
開庁式には市内各地の学校や寺院の関係者、近隣の村長ら名士が一堂に会し鹿児島市の門出を祝った。初代市長の上村行徴(ゆきあき)は「勤勉不撓(ふとう)の精神を以(もっ)て将来市民の幸福を増進」するとあいさつ。その上で「聖旨に報い奉り又閣下が懇諭に違(たが)うなき」を誓った。地方自治を喜び、市民への忠誠を宣言した。
明治政府の発足以降、たびたび地方の再編が繰り返されたが、この時発足した鹿児島市が現在に至る。あいさつの行間から「国の方から与えられ地方自治制度であることを看取することができる」(鹿児島市史II)と指摘され、各種権限は限定された自治体と言えた。鹿児島市は、鹿児島郡に属していた50町村をまとめた区域で発足(上町、西田など約14平方キロ)。当時の人口は4万7512人だった(鹿児島市史II)。
甲南大学名誉教授の高寄昇三さん(84)=地方財政=は「明治期の地方史は中央の『支配』が確立していった過程」とみる。
□ ■ □
鹿児島市発足の前年、明治21年に公布されたのが、「市制・町村制」だ。三新法から10年の月日がたっていた。人口2万5000人以上の都市を基準に市が置かれることとなり、京都市のほか全国35カ所が施行地とされた。
政府そして県の“下部組織”としての色彩が強い市制だが、意欲のある市長の下で積極的な施策に打って出た自治体もあった。その一つが京都市だ。時代は下るものの、西郷隆盛の子・西郷菊次郎が2代目の市長に就いた明治後期に目覚ましい発展を遂げた。
隆盛と愛加那との間に生まれた菊次郎は、長じて米国に留学。西南戦争で薩軍に加わって、右脚を負傷し投降した。その後、外務省に入省し台湾に赴任するなどした。
帰国後、京都市長となった菊次郎は厳しい財政事情の中、政府に頼るだけでなく、市単位の利用は当時珍しかった外国債に目を付けた。明治42(1909)年には市税収入の34倍に当たる仏国の外債発行を取り付け、第2琵琶湖疏水(そすい)・上水道・道路拡幅、電気軌道敷設の3大事業を敢行。東京への“遷都”以降、衰退の一途をたどっていた日本の古都を生まれ変わらせた。
高寄さんは「先見の明があった市長が明治期にいた自治体こそ、その後の発展が著しく現代にまでつながっている」と指摘した。
政府そして県の“下部組織”としての色彩が強い市制だが、意欲のある市長の下で積極的な施策に打って出た自治体もあった。その一つが京都市だ。時代は下るものの、西郷隆盛の子・西郷菊次郎が2代目の市長に就いた明治後期に目覚ましい発展を遂げた。
隆盛と愛加那との間に生まれた菊次郎は、長じて米国に留学。西南戦争で薩軍に加わって、右脚を負傷し投降した。その後、外務省に入省し台湾に赴任するなどした。
帰国後、京都市長となった菊次郎は厳しい財政事情の中、政府に頼るだけでなく、市単位の利用は当時珍しかった外国債に目を付けた。明治42(1909)年には市税収入の34倍に当たる仏国の外債発行を取り付け、第2琵琶湖疏水(そすい)・上水道・道路拡幅、電気軌道敷設の3大事業を敢行。東京への“遷都”以降、衰退の一途をたどっていた日本の古都を生まれ変わらせた。
高寄さんは「先見の明があった市長が明治期にいた自治体こそ、その後の発展が著しく現代にまでつながっている」と指摘した。