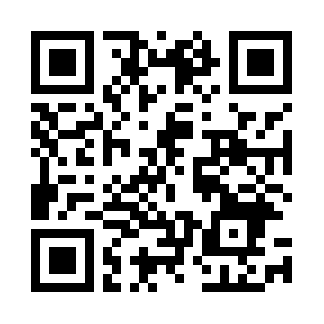第9部

大久保政権
政変後、士族対策に直面
「後任参議や政府組織はどうすべきか」―。明治6年(1873)年10月22日、大久保利通は右大臣岩倉具視からの手紙を受け、思いを巡らせていた。征韓論政変によって西郷隆盛が辞表を出す前日のことだ。大久保は“盟友”を知り尽くしており辞職を見越していた。
3日後、参議が各省のトップである卿を兼ねる参議・卿兼任制が導入された。岩倉使節団の留守をあずかった西郷らの政府は、参議らでつくる中枢機関・正院の権限が弱く、近代化政策を競う各省の対立を統制できなかった。その反省も踏まえ、大久保が持論を反映させた政府強化策だった。
翌11月、勧業・警察・地方の三行政を担う最大官庁「内務省」が創設され、そのトップ内務卿に大久保が座った。国士舘大学の勝田政治教授は「大久保は特に勧業を重視した。内務省は征韓論政変後の国家目標・民力養成の実施機関として位置付けられた」と指摘する。
西郷らの後任、新参議に外務卿・寺島宗則、工部卿・伊藤博文らが加わった。「藩閥政治」と批判もされたが、大久保は個人的関係よりも仕事のできる人物を最優先し、大隈重信(大蔵卿)と伊藤が両翼を支える体制は後に「大久保政権」と称される。巨大な権力をもつ内務省と大久保がその後の国政をリードしたが、始動は混迷の中にあった。
3日後、参議が各省のトップである卿を兼ねる参議・卿兼任制が導入された。岩倉使節団の留守をあずかった西郷らの政府は、参議らでつくる中枢機関・正院の権限が弱く、近代化政策を競う各省の対立を統制できなかった。その反省も踏まえ、大久保が持論を反映させた政府強化策だった。
翌11月、勧業・警察・地方の三行政を担う最大官庁「内務省」が創設され、そのトップ内務卿に大久保が座った。国士舘大学の勝田政治教授は「大久保は特に勧業を重視した。内務省は征韓論政変後の国家目標・民力養成の実施機関として位置付けられた」と指摘する。
西郷らの後任、新参議に外務卿・寺島宗則、工部卿・伊藤博文らが加わった。「藩閥政治」と批判もされたが、大久保は個人的関係よりも仕事のできる人物を最優先し、大隈重信(大蔵卿)と伊藤が両翼を支える体制は後に「大久保政権」と称される。巨大な権力をもつ内務省と大久保がその後の国政をリードしたが、始動は混迷の中にあった。
□ ■ □
外征を否定したばかりの大久保新政権だったが、相次いで台湾問題が降りかかった。明治4年、琉球住民が台湾の原住民族(生蕃(せいばん))に殺害された事件があり、征韓論に期待していた士族らの不満は「征台」に向かったのだ。清政府が「生蕃は政教(統治)の及ばない“化外”の民」としたことで、日本政府は明治7年2月6日、台湾出兵を決定した。清とは平和的交渉を前提にした。
一方、国内には波紋が広がった。征韓論政変で下野した元参議板垣退助、江藤新平、後藤象二郎、副島種臣らは同年1月、民撰(みんせん)議院(国会)設立建白書を提出。閣議決定した征韓論を不当に覆した大久保や岩倉を「天下の公議」を抑え付ける有司専制(少数の官吏による専制独裁)として非難した。建白書は納税者は政策決定に参加する権利がある、とも主張。新聞「日新真事誌」に全文掲載され論争を巻き起こし、自由民権運動へと発展していった。
2月、建白書に署名した江藤が佐賀の不平士族に担がれ、「佐賀の乱」を起こした。大久保の対応は早かった。全権委任を受けるや、すぐさま鎮圧へ佐賀に向かった。汽船で大阪、東京から兵が結集し、反乱軍は月末には壊滅状態となった。4月13日、江藤は死刑判決を受け即日執行、さらし首となった。
大久保は日記に「江藤の醜体笑止」と記した。迅速で冷酷な処置は、大久保の江藤への「私怨から」とも指摘されたが、明治大学の落合弘樹教授は「反乱が各地へ波及するのを防ぎ、処分が長引くことで江藤らに寛大な処置を求める世論が生まれることを阻止する狙いがあった」とみる。
一方、国内には波紋が広がった。征韓論政変で下野した元参議板垣退助、江藤新平、後藤象二郎、副島種臣らは同年1月、民撰(みんせん)議院(国会)設立建白書を提出。閣議決定した征韓論を不当に覆した大久保や岩倉を「天下の公議」を抑え付ける有司専制(少数の官吏による専制独裁)として非難した。建白書は納税者は政策決定に参加する権利がある、とも主張。新聞「日新真事誌」に全文掲載され論争を巻き起こし、自由民権運動へと発展していった。
2月、建白書に署名した江藤が佐賀の不平士族に担がれ、「佐賀の乱」を起こした。大久保の対応は早かった。全権委任を受けるや、すぐさま鎮圧へ佐賀に向かった。汽船で大阪、東京から兵が結集し、反乱軍は月末には壊滅状態となった。4月13日、江藤は死刑判決を受け即日執行、さらし首となった。
大久保は日記に「江藤の醜体笑止」と記した。迅速で冷酷な処置は、大久保の江藤への「私怨から」とも指摘されたが、明治大学の落合弘樹教授は「反乱が各地へ波及するのを防ぎ、処分が長引くことで江藤らに寛大な処置を求める世論が生まれることを阻止する狙いがあった」とみる。
□ ■ □
参議を辞職した西郷は建白に加わらず、鹿児島に戻った。佐賀の乱で逃走した江藤が明治7年3月、援軍を求め、指宿・鰻温泉に訪ねてきた。その際、西郷は「私の言うようになさらんと、あてが違いますぞ」と諭したとされる。
西郷の心境について、落合教授は「政府に歯向かうつもりはなく、後の国づくりは大久保ら後輩に任せ、自分は農業や人材育成に専念するつもりだったのではないか。しかし、国の危機の際は身をていする覚悟をもっていた」と推測する。
鹿児島に同年6月、私学校が創設、近衛の除隊兵らを収容した。西郷を慕って鹿児島に帰った篠原国幹が銃隊学校、村田新八が砲隊学校でそれぞれ指導。翌8年4月には吉野開墾社が設立され、西郷自ら開墾に当たった。私学校は無職化した士族の統制を図るため設けられたが、軍人養成学校の性格を帯びた。旧薩摩藩の武器弾薬と合わせ巨大な戦力を温存し、徴兵検査も実施されない「独立国」は、政府にとって脅威だった。
西郷の心境について、落合教授は「政府に歯向かうつもりはなく、後の国づくりは大久保ら後輩に任せ、自分は農業や人材育成に専念するつもりだったのではないか。しかし、国の危機の際は身をていする覚悟をもっていた」と推測する。
鹿児島に同年6月、私学校が創設、近衛の除隊兵らを収容した。西郷を慕って鹿児島に帰った篠原国幹が銃隊学校、村田新八が砲隊学校でそれぞれ指導。翌8年4月には吉野開墾社が設立され、西郷自ら開墾に当たった。私学校は無職化した士族の統制を図るため設けられたが、軍人養成学校の性格を帯びた。旧薩摩藩の武器弾薬と合わせ巨大な戦力を温存し、徴兵検査も実施されない「独立国」は、政府にとって脅威だった。