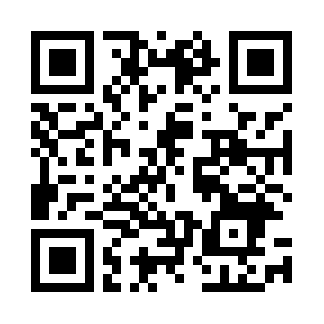第11部

プロローグ
民撰議院設立建白書
「政権の帰する所を察するに、上帝室に在らず、下人民に在らず、しかして独り有司に帰す。(中略)天下の公議を張るは、民撰(みんせん)議院を立(たつ)るにある」
明治7(1874)年1月18日、日刊紙「日新真事誌」にある建白書が掲載された。自由民権運動が活発化する端緒となった「民撰議院設立建白書」だ。当時は議会や選挙はなく、意見や政策を取り入れるために政府が建白書提出を奨励していた。
提出したのは、前参議の板垣退助、江藤新平、副島種臣ら8人。前年に征韓論争を巡る政変(明治6年政変)で敗れ、下野した面々だった。この建白書を入手した「日新真事誌」が全文を掲載。世間に広く知られることになった。
建白書では、権力を握るのは天皇や民ではなく、藩閥出身の一握りの“有司”(官僚)だと批判。政治は朝令暮改、私情で決められ、定まった方針がないと指摘、国家崩壊を防ぐには選挙で選ばれた議会開設が必要だと訴えた。
板垣とともに下野した西郷隆盛は、建白書提出には参加しなかった。板垣が監修した「自由党史」によると、西郷は民撰議院の設立を主張した板垣に対し、手をたたいて賛意を示したという。
折しも、政府は勧業・警察・地方の3行政を担う最大官庁、内務省を設置。内務卿に就いた大久保利通が巨大な権力を握っていた。これに対して、建白書提出の直前には、高知士族による岩倉具視の暗殺未遂や、東京で政府転覆を狙った放火事件なども発生、不穏な動きが広まっていた。
明治7(1874)年1月18日、日刊紙「日新真事誌」にある建白書が掲載された。自由民権運動が活発化する端緒となった「民撰議院設立建白書」だ。当時は議会や選挙はなく、意見や政策を取り入れるために政府が建白書提出を奨励していた。
提出したのは、前参議の板垣退助、江藤新平、副島種臣ら8人。前年に征韓論争を巡る政変(明治6年政変)で敗れ、下野した面々だった。この建白書を入手した「日新真事誌」が全文を掲載。世間に広く知られることになった。
建白書では、権力を握るのは天皇や民ではなく、藩閥出身の一握りの“有司”(官僚)だと批判。政治は朝令暮改、私情で決められ、定まった方針がないと指摘、国家崩壊を防ぐには選挙で選ばれた議会開設が必要だと訴えた。
板垣とともに下野した西郷隆盛は、建白書提出には参加しなかった。板垣が監修した「自由党史」によると、西郷は民撰議院の設立を主張した板垣に対し、手をたたいて賛意を示したという。
折しも、政府は勧業・警察・地方の3行政を担う最大官庁、内務省を設置。内務卿に就いた大久保利通が巨大な権力を握っていた。これに対して、建白書提出の直前には、高知士族による岩倉具視の暗殺未遂や、東京で政府転覆を狙った放火事件なども発生、不穏な動きが広まっていた。
□ ■ □
民権派が目指したのは、憲法に基づく国家体制(立憲政体)や国会の開設だった。「広く会議を興し、万機公論に決すべし」と掲げた「五箇条の御誓文」の精神にも通じる主張だった。
民撰議院建白書の反響は大きく、新聞や雑誌を舞台に論争が活発化した。自由民権運動の本格的な幕開けとなった。
当時、民撰議院設立を原則的に否定する論者はほとんどいなかったが、「時期尚早」と「即時設立」で議論が分かれた。新政府を中心に尚早派は、まだ日本人が開明的ではなく、権利や義務を理解できない状況では十分機能しないなどと主張。一方の即時設立派は、議会開設に伴い政治に関わることで開明化が進むと訴えた。
建白書の提出者が、3カ月前まで政府中枢にいたことへの批判もあった。森有礼は「建言した人々は在官の時と今日とを比べて、その差異があるか」と指摘。政府から追われたことへの意趣返しと見られたのも無理はなかった。
論争の雌雄は容易には決まらなかったが、有司専制批判と民撰議院設立の必要性は、見る間に民衆へと浸透していった。
民撰議院建白書の反響は大きく、新聞や雑誌を舞台に論争が活発化した。自由民権運動の本格的な幕開けとなった。
当時、民撰議院設立を原則的に否定する論者はほとんどいなかったが、「時期尚早」と「即時設立」で議論が分かれた。新政府を中心に尚早派は、まだ日本人が開明的ではなく、権利や義務を理解できない状況では十分機能しないなどと主張。一方の即時設立派は、議会開設に伴い政治に関わることで開明化が進むと訴えた。
建白書の提出者が、3カ月前まで政府中枢にいたことへの批判もあった。森有礼は「建言した人々は在官の時と今日とを比べて、その差異があるか」と指摘。政府から追われたことへの意趣返しと見られたのも無理はなかった。
論争の雌雄は容易には決まらなかったが、有司専制批判と民撰議院設立の必要性は、見る間に民衆へと浸透していった。
□ ■ □
明治6年政変後、西郷が桐野利秋や篠原国幹らを引き連れて鹿児島に帰ったように、板垣も同郷人とともに高知に戻り、「立志社」を結成した。民権思想の普及と同時に、“失業者”となった士族の没落や暴発を防ぐ対策でもあった。士族授産事業に加え、教育機関の立志学舎を設立。英語や西洋政治思想など高水準の教育を行い、新聞などを発行した。
鹿児島の私学校同様、政府は立志社への警戒を強めた。実際、明治10(77)年に西南戦争が起こると、立志社の一部で挙兵論が高まり、首謀者が逮捕された(立志社の獄)。ただ、板垣は立たず、立志社は言論路線を守った。
高知市立自由民権記念館の筒井秀一館長(62)は「高知の動きに天下は注目したが、板垣にとって武力は第1選択肢ではなかった。これ以上血を流したくなかったのかもしれない」と推察。「高知では民権運動を担う若手や思想が育っていた。板垣のすごさは新たな息吹に懸け、若手に“出番”を与えたことだ」と語る。
言論路線にかじを切った高知は、板垣の下で自由民権運動の中心的役割を果たしていった。
鹿児島の私学校同様、政府は立志社への警戒を強めた。実際、明治10(77)年に西南戦争が起こると、立志社の一部で挙兵論が高まり、首謀者が逮捕された(立志社の獄)。ただ、板垣は立たず、立志社は言論路線を守った。
高知市立自由民権記念館の筒井秀一館長(62)は「高知の動きに天下は注目したが、板垣にとって武力は第1選択肢ではなかった。これ以上血を流したくなかったのかもしれない」と推察。「高知では民権運動を担う若手や思想が育っていた。板垣のすごさは新たな息吹に懸け、若手に“出番”を与えたことだ」と語る。
言論路線にかじを切った高知は、板垣の下で自由民権運動の中心的役割を果たしていった。