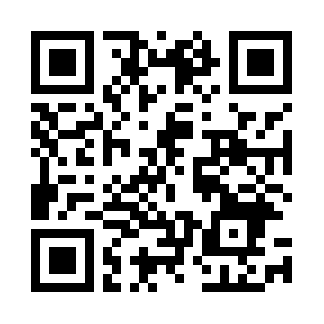第2部

プロローグ
新政府、国際法則り対処
「下がれ、下がれ」―。慶応4(1868)年1月11日昼すぎ、岡山備前藩兵隊列は、先頭の掛け声とともに神戸村(兵庫県神戸市)を進んでいた。西宮へ警備に出向く途中、村人は土下座したが、外国人は物珍しげに見物していた。その態度を不遜とみて、備前兵は敵意をあらわにした。
事件は外国人の居住や貿易が認められた居留地近くの三宮神社前で起こった。仏人兵が制止を振り切り、隊列を横切ったのだ。見とがめた藩兵がやりで一撃、仏兵側が短銃で応戦の構えを見せたのを機に一斉に銃撃戦が始まった。領事館に逃げる外国人を追って射撃が続いた。その後「神戸事件」と呼ばれた。
神戸港の各国軍艦の警備兵が続々上陸、戦闘が起こったが、双方に死者は出なかった。だが、激怒した駐日英国公使ハリー・パークス主導で列強国は日本船6隻を拿捕(だほ)、居留地一帯を占領下に置く強硬策に出た。「日本全体に重大な紛争を引き起こすかもしれない」との声明で、開戦すらにおわせた。
事件は外国人の居住や貿易が認められた居留地近くの三宮神社前で起こった。仏人兵が制止を振り切り、隊列を横切ったのだ。見とがめた藩兵がやりで一撃、仏兵側が短銃で応戦の構えを見せたのを機に一斉に銃撃戦が始まった。領事館に逃げる外国人を追って射撃が続いた。その後「神戸事件」と呼ばれた。
神戸港の各国軍艦の警備兵が続々上陸、戦闘が起こったが、双方に死者は出なかった。だが、激怒した駐日英国公使ハリー・パークス主導で列強国は日本船6隻を拿捕(だほ)、居留地一帯を占領下に置く強硬策に出た。「日本全体に重大な紛争を引き起こすかもしれない」との声明で、開戦すらにおわせた。
□ ■ □

神戸事件発生地の石碑。三宮神社の境内に立つ=神戸市中央区
鳥羽・伏見の戦いが終わってわずか5日後、新政府にとって初の外交問題だった。戊辰戦争緒戦に勝利し、前将軍・徳川慶喜追討令を発したとはいえ、旧幕府勢力はいまだ恭順しておらず、諸藩の動向も不透明な情勢。国を二分する状況で、対外紛争をしている場合ではなかった。
外交を扱う「外国事務掛(がかり)」が1月9日、設置されたばかりだった。参与の東久世通禧(みちとみ)、岩下方平(薩摩藩)らが任じられた。早速、大坂に飛んだ岩下は11日の事件当夜、寺島宗則、五代友厚ら薩摩の主要藩士と対応を協議した。同藩外交顧問のフランス貴族モンブランも加わった。
鹿児島県史料に残る結果概要はこうだ。「万国公法では先に手を出した方に非があるので、備前藩から発砲したのなら、下手人と賠償金を出さなければならない。備前が承知しなければ、朝命で処罰すればよい。そうすれば外国人も公平な処置に感銘を受け、日本のためにもなるだろう」
決めたのは「異情に通じ候(そうろう)方々」だった。鹿児島純心女子大名誉教授の犬塚孝明さん(近代日本政治外交史)は著書で「岩下、寺島、五代の面々であり、モンブランが意見を付け加えた」とみる(「幕末 独立を守った"現実外交"」)。
3人は幕末に渡欧、英国をはじめ各国との外交交渉を経験していた。当時の世界レベルでの現場を踏んだ寺島らは、西洋の価値観に基づく近代国際法を指す「万国公法」に通じていた。
外交を扱う「外国事務掛(がかり)」が1月9日、設置されたばかりだった。参与の東久世通禧(みちとみ)、岩下方平(薩摩藩)らが任じられた。早速、大坂に飛んだ岩下は11日の事件当夜、寺島宗則、五代友厚ら薩摩の主要藩士と対応を協議した。同藩外交顧問のフランス貴族モンブランも加わった。
鹿児島県史料に残る結果概要はこうだ。「万国公法では先に手を出した方に非があるので、備前藩から発砲したのなら、下手人と賠償金を出さなければならない。備前が承知しなければ、朝命で処罰すればよい。そうすれば外国人も公平な処置に感銘を受け、日本のためにもなるだろう」
決めたのは「異情に通じ候(そうろう)方々」だった。鹿児島純心女子大名誉教授の犬塚孝明さん(近代日本政治外交史)は著書で「岩下、寺島、五代の面々であり、モンブランが意見を付け加えた」とみる(「幕末 独立を守った"現実外交"」)。
3人は幕末に渡欧、英国をはじめ各国との外交交渉を経験していた。当時の世界レベルでの現場を踏んだ寺島らは、西洋の価値観に基づく近代国際法を指す「万国公法」に通じていた。
□ ■ □
全権を委ねられた東久世は1月15日、神戸運上所(税関)で英米仏など列強6カ国代表と会見した。諸外国との初の公式折衝で、天皇親政と幕府の結んだ条約の継承が通告された。
岩下、寺島、吉井友実のほか海外経験のあった伊藤博文(長州藩)らが列席した。寺島は事件翌日に外国事務取調掛(とりしらべがかり)を任され、早々に英国領事館を訪問。パークスや書記官アーネスト・サトウに新政府の外交や対応方針を伝えた。
「文明国の所業とは思えない」と詰め寄る諸外国代表に、東久世は「万国公法に則(のっと)り、天皇の責任で処置に当たる」と明言。責任を認め、外国人の生命・財産保護、備前藩の処罰を約束した。先の在坂薩摩藩士の方針通りだった。
外国側から「発砲命令者の死罪」を求められ、新政府はもめた。日本の慣習に沿った備前藩の行動を、西洋のルールで裁くことへの不満があった。副総裁の岩倉具視は同藩に「国家のため」などと因果を含めた。伊藤は五代あての書簡で速やかな解決を促しており、五代は相当骨を折ったという。最終的に備前藩は処分を受け入れ、2月9日、命令責任者・瀧善三郎の切腹で解決した。
パークスは、新政府の迅速な対処に統治能力を認め、米国公使も毅然(きぜん)と対処できなかった旧幕府を引き合いに「(新政府は)交際を深めるに値する」と好感した。解決まで1カ月足らず。対処を見誤れば軍事介入の恐れもあったが、危機は去った。薩摩出身者らの経験や現実主義によって国際的承認を得た、近代外交の幕開けとなった。
岩下、寺島、吉井友実のほか海外経験のあった伊藤博文(長州藩)らが列席した。寺島は事件翌日に外国事務取調掛(とりしらべがかり)を任され、早々に英国領事館を訪問。パークスや書記官アーネスト・サトウに新政府の外交や対応方針を伝えた。
「文明国の所業とは思えない」と詰め寄る諸外国代表に、東久世は「万国公法に則(のっと)り、天皇の責任で処置に当たる」と明言。責任を認め、外国人の生命・財産保護、備前藩の処罰を約束した。先の在坂薩摩藩士の方針通りだった。
外国側から「発砲命令者の死罪」を求められ、新政府はもめた。日本の慣習に沿った備前藩の行動を、西洋のルールで裁くことへの不満があった。副総裁の岩倉具視は同藩に「国家のため」などと因果を含めた。伊藤は五代あての書簡で速やかな解決を促しており、五代は相当骨を折ったという。最終的に備前藩は処分を受け入れ、2月9日、命令責任者・瀧善三郎の切腹で解決した。
パークスは、新政府の迅速な対処に統治能力を認め、米国公使も毅然(きぜん)と対処できなかった旧幕府を引き合いに「(新政府は)交際を深めるに値する」と好感した。解決まで1カ月足らず。対処を見誤れば軍事介入の恐れもあったが、危機は去った。薩摩出身者らの経験や現実主義によって国際的承認を得た、近代外交の幕開けとなった。