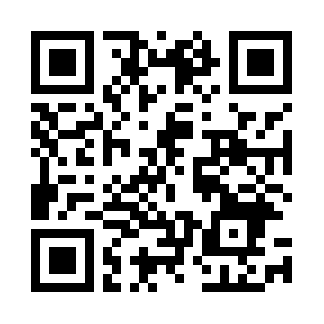第6部

プロローグ
廃仏毀釈

慈眼寺を守っていた仁王像。腕や顔の傷が痛々しい=鹿児島市の慈眼寺公園
筋肉が盛り上がった肩口に、容赦なくのみが振り下ろされた。憤怒で見開かれた目に、太い首に、次々と刃や石がたたきつけられた―。明治の初め、全国でそんな光景が繰り広げられたに違いない。
鹿児島市の慈眼寺公園に立つ石造の仁王像は、失われた太い腕の断面が痛々しい。鼻や足先もなく満身創痍(そうい)だ。飛鳥時代の創建とされ、かつては薩摩三大寺に数えられた慈眼寺の門を守っていたが、伽藍(がらん)は今や跡形もない。
指宿市の光明禅寺の本尊は鎌倉時代の阿弥陀像。150年ぶりに美しくよみがえった。数年前まで表面が青黒く変色し、首や胸は陥没、足先も欠けていた。難を免れるため、馬糞(ばふん)の中に隠されたのだった。「僧が殺され、檀家(だんか)が命がけで持ち出したと聞いた」と野口良雄住職(68)。「よほどの危険があったのだろう。廃仏とはそこまで激しいものだったのか」
鹿児島市の慈眼寺公園に立つ石造の仁王像は、失われた太い腕の断面が痛々しい。鼻や足先もなく満身創痍(そうい)だ。飛鳥時代の創建とされ、かつては薩摩三大寺に数えられた慈眼寺の門を守っていたが、伽藍(がらん)は今や跡形もない。
指宿市の光明禅寺の本尊は鎌倉時代の阿弥陀像。150年ぶりに美しくよみがえった。数年前まで表面が青黒く変色し、首や胸は陥没、足先も欠けていた。難を免れるため、馬糞(ばふん)の中に隠されたのだった。「僧が殺され、檀家(だんか)が命がけで持ち出したと聞いた」と野口良雄住職(68)。「よほどの危険があったのだろう。廃仏とはそこまで激しいものだったのか」
□ ■ □

馬糞の中に隠されていたという阿弥陀像。顔の漆や螺髪(らほつ、巻き貝のような形の頭髪)の一部など腐食した部分を取り除き、美しくなった=指宿市の光明禅寺
これほどまでの過激な破壊や全国的な仏教排斥が、なぜ起こったのか。
慶応3(1867)年、「王政復古」を宣言して成立した新政府だが、天皇中心の中央集権国家をつくることが第一義となった。西洋列強に対峙(たいじ)する近代国家建設を目指しながら、時代に逆行するかのようにその精神的な支柱に「勤王思想」をすえ、神に頼らざるを得ない事情があった。
直接的なきっかけは、慶応4年3月、神社から仏像や仏具を取り払うよう命じた、いわゆる「神仏判然令」(分離令)だった。皇室の権威を伝え、国民統合を図ろうと、古代の天皇や祖神をまつる神道の国教化が図られたのだ。
それまでの日本における宗教観はいわゆる「神仏習合」であった。神道は平安時代以降、仏教と密接に結びつき、仏が神に姿を変えて現れるとの「本地垂迹(ほんじすいじゃく)説」に基づいて神と仏、神社と寺が共存。神の本性は仏であるとして、神社は寺の下に、神官は僧の下に位置づけられていた。
日本古来の神々に対し、仏は後で大陸から入ってきた新参者。「神武創業の始め」には存在し得ない。さらにその上に仏がいては、神と皇室の権威が損なわれる。新政府は、千年続いた神仏習合の宗教観を変える必要に迫られた。背景には、平田篤胤(あつたね)に端を発する復古神道や水戸学の流行があり、武士に限らず庶民にも「勤皇」が浸透していた。
神仏分離の発令3日後、比叡山の鎮守、近江坂本の日吉大社に神官や武士ら120人が乱入したのが、「廃仏毀釈」の始めとされる。御神体となっていた仏像や経典を破壊、焼却した。仏像の顔に弓矢を射て喜んだともいう。抑圧されていた神官らが、長年の鬱積(うっせき)を爆発させたのだった。
「破壊せよ」との命令こそなかったが、都のそばで起きた事件は衝撃を与えた。暴挙に反感を抱く者もいたが、瞬く間にこの動きが広がった。幕府による民衆支配として寺請(てらうけ)制度(寺に檀家として登録、住民票代わりに掌握する手段)があり、これが封建支配の象徴のように思われていた。また大寺院などが幕府権力と癒着し腐敗していたこともあり、「寺=既得権益を守る保守階層」との認識もあった。慶応4年は9月改元され明治元年となるが、実質的に新政府も黙認したことで、熱病のように全国へ波及した。
慶応3(1867)年、「王政復古」を宣言して成立した新政府だが、天皇中心の中央集権国家をつくることが第一義となった。西洋列強に対峙(たいじ)する近代国家建設を目指しながら、時代に逆行するかのようにその精神的な支柱に「勤王思想」をすえ、神に頼らざるを得ない事情があった。
直接的なきっかけは、慶応4年3月、神社から仏像や仏具を取り払うよう命じた、いわゆる「神仏判然令」(分離令)だった。皇室の権威を伝え、国民統合を図ろうと、古代の天皇や祖神をまつる神道の国教化が図られたのだ。
それまでの日本における宗教観はいわゆる「神仏習合」であった。神道は平安時代以降、仏教と密接に結びつき、仏が神に姿を変えて現れるとの「本地垂迹(ほんじすいじゃく)説」に基づいて神と仏、神社と寺が共存。神の本性は仏であるとして、神社は寺の下に、神官は僧の下に位置づけられていた。
日本古来の神々に対し、仏は後で大陸から入ってきた新参者。「神武創業の始め」には存在し得ない。さらにその上に仏がいては、神と皇室の権威が損なわれる。新政府は、千年続いた神仏習合の宗教観を変える必要に迫られた。背景には、平田篤胤(あつたね)に端を発する復古神道や水戸学の流行があり、武士に限らず庶民にも「勤皇」が浸透していた。
神仏分離の発令3日後、比叡山の鎮守、近江坂本の日吉大社に神官や武士ら120人が乱入したのが、「廃仏毀釈」の始めとされる。御神体となっていた仏像や経典を破壊、焼却した。仏像の顔に弓矢を射て喜んだともいう。抑圧されていた神官らが、長年の鬱積(うっせき)を爆発させたのだった。
「破壊せよ」との命令こそなかったが、都のそばで起きた事件は衝撃を与えた。暴挙に反感を抱く者もいたが、瞬く間にこの動きが広がった。幕府による民衆支配として寺請(てらうけ)制度(寺に檀家として登録、住民票代わりに掌握する手段)があり、これが封建支配の象徴のように思われていた。また大寺院などが幕府権力と癒着し腐敗していたこともあり、「寺=既得権益を守る保守階層」との認識もあった。慶応4年は9月改元され明治元年となるが、実質的に新政府も黙認したことで、熱病のように全国へ波及した。
□ ■ □
薩摩藩の廃仏は一足早く、幕末から始まっていた。藩政改革を進めていた家老桂久武の提案で、慶応2年に「上知」が行われた。寺領を没収し、藩財政強化や藩士へ分配するという目的だった。当初は島津家の菩提寺(ぼだいじ)や勅願所などの大寺は例外として残された。
明治2年、忠義夫人の葬儀を機に島津家が神道へ転向して状況が一変。菩提寺の福昌寺や大乗院、朝廷との縁が深い坊津の一乗院、慈眼寺とあった大寺が廃寺となった。初代忠久の父とされる源頼朝の遺髪は寺から花尾神社に移され、戦国の雄・義弘の妙円寺は徳重神社と名を変えた。
薩摩大隅日向にまたがる領内1066寺はことごとく消滅、僧侶2964人は還俗(げんぞく)(俗世に戻ること)、兵士に転身した者もあった。県歴史資料センター黎明館の栗林文夫調査史料室長(54)は「寺請制度が機能しなかったなど複数の要因もあるが、すべての寺が消えたのは鹿児島だけ」。
皇室や公家と縁の深い京、奈良の大寺も免れなかった。大多数の公家の祖、藤原氏の氏寺である興福寺(奈良)はすべての僧が退去して無人となり、五重塔が売り出された。由緒ある寺の古仏が焼かれて金品をとられ、千年以上前の経典が土産物の包み紙になった。廃寺から奪われた仏像が、外国に売り飛ばされることもあった。
明治2年、忠義夫人の葬儀を機に島津家が神道へ転向して状況が一変。菩提寺の福昌寺や大乗院、朝廷との縁が深い坊津の一乗院、慈眼寺とあった大寺が廃寺となった。初代忠久の父とされる源頼朝の遺髪は寺から花尾神社に移され、戦国の雄・義弘の妙円寺は徳重神社と名を変えた。
薩摩大隅日向にまたがる領内1066寺はことごとく消滅、僧侶2964人は還俗(げんぞく)(俗世に戻ること)、兵士に転身した者もあった。県歴史資料センター黎明館の栗林文夫調査史料室長(54)は「寺請制度が機能しなかったなど複数の要因もあるが、すべての寺が消えたのは鹿児島だけ」。
皇室や公家と縁の深い京、奈良の大寺も免れなかった。大多数の公家の祖、藤原氏の氏寺である興福寺(奈良)はすべての僧が退去して無人となり、五重塔が売り出された。由緒ある寺の古仏が焼かれて金品をとられ、千年以上前の経典が土産物の包み紙になった。廃寺から奪われた仏像が、外国に売り飛ばされることもあった。