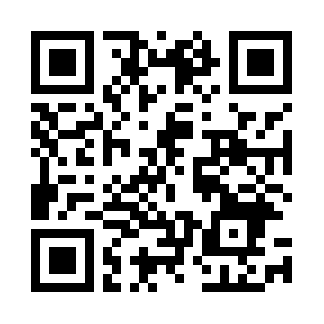第7部

プロローグ
初代文部大臣
「ハロー」「グッド・モーニン」。明治3(1870)年、鹿児島城下に声が響いた。英米の留学から帰国した森有礼が、廃仏毀釈(きしゃく)で廃寺となった興国寺跡に開いた英学塾だ。学問は男子だけがするのが「当然」だった時代に女子も机を並べていた。
明治政府に出仕し、当初外国官権判事に任じられた森は、すぐさま学校取調(とりしらべ)(兼務)にも任命。だが明治2年、自身が提案した「廃刀案」が士族らの大反対に遭って政府を去り、鹿児島へ帰郷を余儀なくされた。
3年間の海外留学を経ていた森は「文明化はまず教育から」と考え、鹿児島医学校兼病院の院長だった英国人医師ウィリアム・ウィリスに、本場の発音の指導を依頼するよう上申するなど、郷土の後進育成に燃えていた。
鹿児島城下で生まれた森は洋学校・開成所などで学び、元治2(65)年に18歳で薩摩藩英国留学生に選ばれ、海を渡った。ロンドン大学で勉学に励み、その後に移った米国でも欧米の教育現場に触れる貴重な経験を得た。女子教育の重要性も認識し、帰国後いち早く実践した。
鹿児島での英学塾は1年足らず。政府に呼び戻され、日本初の在外外交官として渡米した。米国各界の有識者15人に日本の教育改善について助言を求める書簡を送り、その返書をまとめて「日本における教育」を現地で出版した。
密航者、新島襄を政府留学生に公認するよう斡旋(あっせん)し、米国式の私立学校を日本に設立するよう勧めた。新島の学校は、のち同志社大学となった。一方、女子教育の先駆者で津田塾大学の創設者、津田梅子ら日本初の女子留学生を世話するなど、森は政府の「岩倉使節団」(明治4~6年)や外交折衝の傍ら、教育への“種”をまき続けた。
森には理想があった。日本が文明国として独立維持するには、教育制度を確立し、国家に尽くす人材を育成する必要があると考えていた。
明治政府に出仕し、当初外国官権判事に任じられた森は、すぐさま学校取調(とりしらべ)(兼務)にも任命。だが明治2年、自身が提案した「廃刀案」が士族らの大反対に遭って政府を去り、鹿児島へ帰郷を余儀なくされた。
3年間の海外留学を経ていた森は「文明化はまず教育から」と考え、鹿児島医学校兼病院の院長だった英国人医師ウィリアム・ウィリスに、本場の発音の指導を依頼するよう上申するなど、郷土の後進育成に燃えていた。
鹿児島城下で生まれた森は洋学校・開成所などで学び、元治2(65)年に18歳で薩摩藩英国留学生に選ばれ、海を渡った。ロンドン大学で勉学に励み、その後に移った米国でも欧米の教育現場に触れる貴重な経験を得た。女子教育の重要性も認識し、帰国後いち早く実践した。
鹿児島での英学塾は1年足らず。政府に呼び戻され、日本初の在外外交官として渡米した。米国各界の有識者15人に日本の教育改善について助言を求める書簡を送り、その返書をまとめて「日本における教育」を現地で出版した。
密航者、新島襄を政府留学生に公認するよう斡旋(あっせん)し、米国式の私立学校を日本に設立するよう勧めた。新島の学校は、のち同志社大学となった。一方、女子教育の先駆者で津田塾大学の創設者、津田梅子ら日本初の女子留学生を世話するなど、森は政府の「岩倉使節団」(明治4~6年)や外交折衝の傍ら、教育への“種”をまき続けた。
森には理想があった。日本が文明国として独立維持するには、教育制度を確立し、国家に尽くす人材を育成する必要があると考えていた。
□ ■ □
近代国家への変貌を急ぐ明治政府は、明治4年に教育行政を担う文部省を設置した。欧米式の教育制度を模範として翌年に「学制」、さらに明治12年には「教育令」を公布した。全国で均一な教育制度づくりが進められたが、実情は庶民生活との乖離(かいり)や就学率の低迷など問題も抱え、理想と現実はかけ離れていた。
その後、森は米国から中国や英国での勤務を続け、外交畑を歩んだ。だが、常に教育行政に意見書を出すなど、近代化のための日本人教育が彼の頭を離れることはなかった。明治15年、「教育の基礎を定むるの識見を有するの人」を求めていた伊藤博文は、パリで森と会談し意見一致。日本初の内閣が明治18年、伊藤の下でつくられると、森は初代の文部大臣に指名された。
初等教育から高等教育まで包括的に規定されていた法令を学校の種別ごとに整える「諸学校令」を明治19年制定した。3月の「帝国大学令」を手始めに「小学校令」「中学校令」「師範学校令」を定めた。国の将来を担う優秀な人材養成、専門研究機関として重要視する高等教育に関わる「帝国大学令」は、森自ら筆を握り立案。“帝国”と付けたのも森のアイデアだった(犬塚孝明「森有礼」)。
英国で義務教育が青少年犯罪抑制や国力発展を支えていると知り、小学校令では「普通教育を得せしむるの義務あるものとす」と掲げた。有償だった初等教育は、貧しい家のために無償の小学校簡易課を設置し、小・中学校教科書の検定制も規定した。“皆学”への道筋を着々と描いた。
京都大学大学院教育学研究科の田中智子准教授=日本近現代史=(49)は「壮大すぎて絵に描いた餅になっていた政府の教育制度をやり直して、機能させようとしたのが森だった。法令を触媒にして改革を進めた」と話す。
その後、森は米国から中国や英国での勤務を続け、外交畑を歩んだ。だが、常に教育行政に意見書を出すなど、近代化のための日本人教育が彼の頭を離れることはなかった。明治15年、「教育の基礎を定むるの識見を有するの人」を求めていた伊藤博文は、パリで森と会談し意見一致。日本初の内閣が明治18年、伊藤の下でつくられると、森は初代の文部大臣に指名された。
初等教育から高等教育まで包括的に規定されていた法令を学校の種別ごとに整える「諸学校令」を明治19年制定した。3月の「帝国大学令」を手始めに「小学校令」「中学校令」「師範学校令」を定めた。国の将来を担う優秀な人材養成、専門研究機関として重要視する高等教育に関わる「帝国大学令」は、森自ら筆を握り立案。“帝国”と付けたのも森のアイデアだった(犬塚孝明「森有礼」)。
英国で義務教育が青少年犯罪抑制や国力発展を支えていると知り、小学校令では「普通教育を得せしむるの義務あるものとす」と掲げた。有償だった初等教育は、貧しい家のために無償の小学校簡易課を設置し、小・中学校教科書の検定制も規定した。“皆学”への道筋を着々と描いた。
京都大学大学院教育学研究科の田中智子准教授=日本近現代史=(49)は「壮大すぎて絵に描いた餅になっていた政府の教育制度をやり直して、機能させようとしたのが森だった。法令を触媒にして改革を進めた」と話す。
□ ■ □
大日本帝国憲法発布のその日、明治22(89)年2月11日朝、東京・永田町の屋敷を出る前に森は刺された。暴漢は国粋主義者の西野文太郎(山口県士族)。20年11月、伊勢神宮での不敬事件が原因だった。森が土足で殿上に上がり、ステッキで御簾(みす)を上げて中をのぞいた、と流布された。神道国教化に反対する森に反感を持つ神職のねつ造という説もある。襲った西野の懐中には、不敬事件を非難する斬奸状(ざんかんじょう)があった。
極端な言動から、森は欧化主義者として世に知られていた。国際社会の一員として認められるため、「貧弱で不確実な伝達手段」の日本語を廃し、英語を公用語とするよう主張。のちに英語国語化論は引き下げたのだが、儒教主義的な教育を主張する守旧派からは警戒され、「洋癖」と目の敵にされていた。
森は翌日、息を引き取った。森とともに明治6年、日本初の啓蒙(けいもう)団体「明六社」をつくった福沢諭吉は新聞に「我国文明のために有為活発なる一個の若政治家を失ひしを惜しむ」と寄せ、志半ばでの死を嘆いた。享年42歳だった。
極端な言動から、森は欧化主義者として世に知られていた。国際社会の一員として認められるため、「貧弱で不確実な伝達手段」の日本語を廃し、英語を公用語とするよう主張。のちに英語国語化論は引き下げたのだが、儒教主義的な教育を主張する守旧派からは警戒され、「洋癖」と目の敵にされていた。
森は翌日、息を引き取った。森とともに明治6年、日本初の啓蒙(けいもう)団体「明六社」をつくった福沢諭吉は新聞に「我国文明のために有為活発なる一個の若政治家を失ひしを惜しむ」と寄せ、志半ばでの死を嘆いた。享年42歳だった。