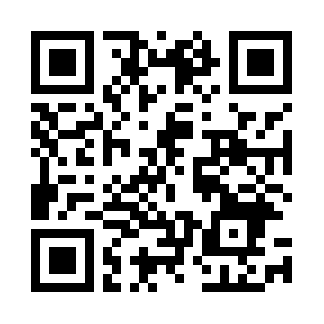第9部

プロローグ
征韓論争
「日本人商人の密貿易を禁じる朝鮮の掲示が公館に出され、日本を『無法之国』とする無礼な文言がある」―。駐在の外務省官員が明治6(1873)年5月、本省に報告した。朝鮮側が設けた「倭館」を、日本側が一方的に自国の所管する公館とするなど“世界基準の対応”を求めて、強硬姿勢に転じた直後のこと。事件が国内に伝わると、「朝鮮は無礼」「討つべし」との征韓論が起こった。
維新後、明治政府は朝鮮と国交を開けなかった。明治初年、朝鮮との交渉を担ってきた対馬藩を通じて「王政復古」を通達。しかし、「皇」「勅」という文字を用いていたため、朝鮮側が拒否したのだ。これは東アジアに、華夷秩序と呼ばれる中国・清を中心にした秩序があったためだ。朝鮮にとって先の文字が使えるのは宗主国である清のみで、朝鮮が日本より下位になることを示す書面は到底認められなかった。
折しも、首脳の半分が岩倉使節団に加わって欧米視察中で、留守をあずかる政府内では参議・板垣退助が軍艦派遣を訴えた。筆頭参議の西郷隆盛は即時派兵に異を唱え、自ら使節になると主張。板垣に宛てた手紙に西郷は「朝鮮側は軽蔑の行動だけでなく使節を暴殺する。その時国民は討つべき罪を知る」と、開戦名分の必要性を説いた。西郷派遣は8月内定。正式決定は使節団帰国を待って行われる運びとなった。
維新後、明治政府は朝鮮と国交を開けなかった。明治初年、朝鮮との交渉を担ってきた対馬藩を通じて「王政復古」を通達。しかし、「皇」「勅」という文字を用いていたため、朝鮮側が拒否したのだ。これは東アジアに、華夷秩序と呼ばれる中国・清を中心にした秩序があったためだ。朝鮮にとって先の文字が使えるのは宗主国である清のみで、朝鮮が日本より下位になることを示す書面は到底認められなかった。
折しも、首脳の半分が岩倉使節団に加わって欧米視察中で、留守をあずかる政府内では参議・板垣退助が軍艦派遣を訴えた。筆頭参議の西郷隆盛は即時派兵に異を唱え、自ら使節になると主張。板垣に宛てた手紙に西郷は「朝鮮側は軽蔑の行動だけでなく使節を暴殺する。その時国民は討つべき罪を知る」と、開戦名分の必要性を説いた。西郷派遣は8月内定。正式決定は使節団帰国を待って行われる運びとなった。
□ ■ □
9月13日、米欧回覧から戻ってきた岩倉具視は、参議と各省庁に「国政整備を整え、民力を厚くすべき」と内治優先の方針を掲げた。一方「留守政府」は、学制、地租改正、徴兵令など急速な開化策を推し進めていた。それらに伴う士族らの強い反発を受け、外征策が打ち出されていた。
朝鮮遣使に強く反対したのは西郷の盟友・大久保利通であった。「国家運営に必要な深謀遠慮を欠く」と批判した。戦争になれば国内が不安定になり、軍事費に伴って財政危機を招きロシア南下の口実を与える―など内治優先から論陣を張った。征韓論争の背景には、留守政府=外征派、使節団組=内治優先派の対立軸があった。
国士舘大学の勝田政治教授(明治維新史)は「(岩倉使節団は)海外視察で日本と欧米諸国との国力差を痛感していた。短期間での西洋文明移入は不可能で、近代化は日本の実情に合わせて行うべきとの共通認識があった」と指摘する。
帰国当初の大久保は、西郷との対決が必至の参議就任を固辞。10月になって、太政(だじょう)大臣三条実美(さねとみ)と岩倉から「使節延期」の念書を取り、参議を引き受けた。しかし、同15日の閣議で西郷派遣が決定した。三条が“変節”したのだ。この頃、体調を崩していたという西郷は内定を変えれば「死をもって国友へ謝罪」と自殺をほのめかしていた。
一方、西郷に対抗して大久保と木戸孝允は辞表を提出した。西郷らには閣議決定の天皇上奏を迫られ、板挟みになった三条は「精神錯乱」し、岩倉が太政大臣代行に就任。これを機に、形勢は大きく変わった。
朝鮮遣使に強く反対したのは西郷の盟友・大久保利通であった。「国家運営に必要な深謀遠慮を欠く」と批判した。戦争になれば国内が不安定になり、軍事費に伴って財政危機を招きロシア南下の口実を与える―など内治優先から論陣を張った。征韓論争の背景には、留守政府=外征派、使節団組=内治優先派の対立軸があった。
国士舘大学の勝田政治教授(明治維新史)は「(岩倉使節団は)海外視察で日本と欧米諸国との国力差を痛感していた。短期間での西洋文明移入は不可能で、近代化は日本の実情に合わせて行うべきとの共通認識があった」と指摘する。
帰国当初の大久保は、西郷との対決が必至の参議就任を固辞。10月になって、太政(だじょう)大臣三条実美(さねとみ)と岩倉から「使節延期」の念書を取り、参議を引き受けた。しかし、同15日の閣議で西郷派遣が決定した。三条が“変節”したのだ。この頃、体調を崩していたという西郷は内定を変えれば「死をもって国友へ謝罪」と自殺をほのめかしていた。
一方、西郷に対抗して大久保と木戸孝允は辞表を提出した。西郷らには閣議決定の天皇上奏を迫られ、板挟みになった三条は「精神錯乱」し、岩倉が太政大臣代行に就任。これを機に、形勢は大きく変わった。
□ ■ □
大久保は、腹心の黒田清隆との間で「秘策」を謀議した(19日付、大久保の日記)。秘策には諸説あるが、宮中工作で明治天皇に「事前に延期論を秘密上奏し、同意を得た。その後、その延期論と閣議決定(使節派遣)の両論を正式上奏させた」(勝田教授)という。
10月24日、天皇は大久保らの思惑通り派遣延期を決断、閣議決定は覆された。西郷は辞表を提出。士族対策を優先した参議の板垣、副島種臣、江藤新平、後藤象二郎もこれにならった。政府の大分裂だった。
西郷を慕う薩摩閥の桐野利秋、篠原国幹や多くの近衛兵が西郷に続き、村田新八ら文官にも波及。岩倉使節団に参加した村田は、大久保が強く慰留したが翻らなかった。
政府に残った参議5人は大隈重信以外、岩倉使節団組だった。勝田教授は「諸外国と肩を並べるには、富国化(民力養成)が最優先と確信していた。非民主的な『秘策』を使ってでも、軍事行動につながる征韓論と対決せざるをえなかった」と指摘する。
これが「征韓論政変」(明治6年政変)と呼ばれることとなった。
10月24日、天皇は大久保らの思惑通り派遣延期を決断、閣議決定は覆された。西郷は辞表を提出。士族対策を優先した参議の板垣、副島種臣、江藤新平、後藤象二郎もこれにならった。政府の大分裂だった。
西郷を慕う薩摩閥の桐野利秋、篠原国幹や多くの近衛兵が西郷に続き、村田新八ら文官にも波及。岩倉使節団に参加した村田は、大久保が強く慰留したが翻らなかった。
政府に残った参議5人は大隈重信以外、岩倉使節団組だった。勝田教授は「諸外国と肩を並べるには、富国化(民力養成)が最優先と確信していた。非民主的な『秘策』を使ってでも、軍事行動につながる征韓論と対決せざるをえなかった」と指摘する。
これが「征韓論政変」(明治6年政変)と呼ばれることとなった。