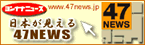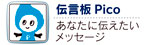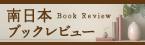健康保険証は新規の発行が停止された。今後、医療機関を受診する際はマイナ保険証、既存の健康保険証、「資格確認書」のうちいずれかを示す。
発行済みの健康保険証は、有効期限内であれば来年12月1日まで使え、これまで通り医療を受けられる。マイナ保険証を持たない人には期限までに保険証の代わりとなる資格確認書が届く。「保険証が使えない」といった誤解や早とちりがないよう国や自治体、関係機関は代替手段の周知と説明に努めてほしい。
マイナ保険証はマイナカードを取得し、利用登録して使う。医療機関や薬局の窓口で読み取り機にかざし、顔認証か暗証番号入力で本人確認する。
マイナカードを持たない人やマイナ保険証の利用登録をしていない人には、自治体や勤務先の健康保険組合から資格確認書が届く。申請は不要で最長5年使え、更新もできる。
資格確認書と名称が似ている「資格情報のお知らせ」が届く人もいる。機器の不具合などでマイナ保険証が読み取れない時に提示するもので、単独では使えないので注意が必要だ。
政府はマイナカードの普及を目指し、2022年秋に健康保険証の廃止とマイナ保険証への一本化を打ち出した。マイナンバーカード取得者に最大2万円分のポイントを付与する「マイナポイント事業」の効果もあり、10月の全人口に占めるマイナカード保有者は75.7%。うちマイナ保険証の利用登録を済ませた人は82.0%に上る。
だが医療機関や薬局でのマイナ保険証の利用率は16%足らずと低迷する。マイナ保険証に別人の情報がひも付けられるミスが相次ぎ、不信感を呼んだことが尾を引いているからだろう。読み取り端末の不具合も続出している。鹿児島県内でも停電で機器が使えなくなるといったトラブルがある。
どの健康保険証を使えばいいか戸惑ったり、マイナ保険証を登録していても認証の操作が不慣れだったりして受診をためらうようなことがあってはならない。移行に当たっては、医療機関も丁寧に説明を尽くしてほしい。
マイナ保険証は、患者が同意すれば医師らが受診歴や薬の処方歴などを閲覧できる。政府は、過剰な投薬の防止など適切な治療につながる利点があると説明している。また患者が負担する医療費が高額になった場合の高額療養費制度は、これまで必要だった申請手続きをせずに支援を受けられるようになり、便利な面はある。
高齢者や障害者などマイナカード取得や顔認証などが必要なマイナ保険証の利用が難しい人も多い。無理に一本化を推し進め、不便が生じる人がいるとしたら本末転倒だ。平将明デジタル相は「誰一人取り残さない」というが、不安は解消していない。
社説
[保険証の移行]代替手段の周知十分に
2025年12月3日 付
-
自民党の高市早苗総裁がきの...(10/22 付)
-
日本維新の会が、自民党との...(10/21 付)
-
2025年の鹿児島県内への...(10/19 付)
-
1994年6月に発足した自...(10/18 付)
-
「人類に与える恩恵は計り知...(10/17 付)
-
世界各地で自国第一主義や排...(10/16 付)
-
パレスチナ自治区ガザの停戦...(10/15 付)
-
宅配ボックスや玄関先に荷物...(10/14 付)
-
石破茂首相が、戦後80年の...(10/12 付)
-
公明党が自民党との連立政権...(10/11 付)
-
佐賀県警のDNA型鑑定不正...(10/10 付)
-
今年のノーベル生理学・医学...(10/9 付)
-
日本ジオパーク委員会が、奄...(10/8 付)
-
パレスチナ自治区ガザの戦闘...(10/7 付)
-
自民党の新総裁に高市早苗前...(10/5 付)
-
鹿児島県議会9月定例会は、...(10/4 付)
-
国内4市とアフリカ諸国の交...(10/3 付)
-
南西諸島周辺で軍事的圧力を...(10/2 付)
-
後期高齢者(75歳以上)の...(10/1 付)
-
老朽化が進む下水道管の調査...(9/30 付)
-
鹿児島銀行(鹿児島市)と肥...(9/28 付)
-
在日米海軍は山口県岩国市の...(9/27 付)
-
自民党総裁選の大きな論点は...(9/26 付)
-
安住の地を求めるユダヤ、土...(9/25 付)
-
米連邦準備制度理事会(FR...(9/24 付)
-
石破茂首相の退陣表明に伴う...(9/23 付)
-
自転車の交通違反に反則金を...(9/21 付)
-
イスラエル軍がパレスチナ自...(9/20 付)
-
陸上自衛隊と米海兵隊が11...(9/19 付)
-
立憲民主党が新体制を発足さ...(9/18 付)
-
都道府県ごとの最低賃金(時...(9/17 付)
-
日本人が慣れ親しむウナギ料...(9/14 付)
-
イスラエルがイスラム組織ハ...(9/13 付)
-
新聞1面の左上に数字が並ん...(9/12 付)
-
およそ5カ月弱にわたった米...(9/11 付)
-
石破茂首相の退陣表明に伴う...(9/10 付)
-
自民党総裁である石破茂首相...(9/8 付)
-
JR九州は2024年度の1...(9/7 付)
-
ストーカー被害を訴えた川崎...(9/6 付)
-
先の大戦は、「枢軸国」と「...(9/5 付)
-
自民党は参院選大敗を検証す...(9/4 付)
-
国の2026年度予算編成に...(9/3 付)
-
教員による児童生徒の盗撮事...(9/2 付)
-
いま憂うつな気持ちになって...(8/31 付)
-
三菱商事を中核とする企業連...(8/30 付)
-
世界全体でプラスチックによ...(8/29 付)
-
九州電力川内原発1、2号機...(8/28 付)
-
韓国の李在明(イ・ジェミョ...(8/27 付)
-
石破内閣の支持率が今月、3...(8/26 付)
-
鹿児島県の2025年産一番...(8/24 付)
-
マダニが媒介するウイルス感...(8/23 付)
-
アフリカの約50カ国の首脳...(8/22 付)
-
トランプ米大統領がウクライ...(8/21 付)
-
8日の記録的大雨で被害を受...(8/20 付)
-
オーストラリア海軍の新型艦...(8/19 付)
-
鹿児島県の2024年度農林...(8/17 付)
-
政府は、コメの事実上の減反...(8/16 付)
-
1945年8月15日、天皇...(8/15 付)
-
東京株式市場の日経平均株価...(8/14 付)
-
鹿児島県本土は8日未明から...(8/13 付)
-
ホテルや旅館の利用者に課す...(8/10 付)
-
原爆があの戦争を終わらせた...(8/9 付)
-
トランプ関税の税率に関し、...(8/8 付)
-
厚生労働省の中央最低賃金審...(8/7 付)
-
1945年8月、広島と長崎...(8/6 付)
-
東京電力が2030年代初頭...(8/5 付)
-
参院選を経て、日本政治の状...(8/3 付)
-
イスラエル軍による封鎖が続...(8/2 付)
-
千人超の生活保護受給者が立...(8/1 付)
-
日米両政府が日本防衛に絡み...(7/31 付)
-
「選挙の顔」をすげ替えれば...(7/30 付)
-
参政党が参院選で当初目標6...(7/29 付)
-
公共交通機関の「空白」に当...(7/27 付)
-
関西電力が美浜原発(福井県...(7/25 付)
-
8回の閣僚協議を経て日米関...(7/24 付)
-
事実上の政権選択選挙とも目...(7/23 付)
-
高速道路での逆走事故が後を...(7/20 付)
-
参院選はあす投票日を迎える...(7/19 付)
-
日本の外交・安全保障の基軸...(7/18 付)
-
日本は2040年ごろに高齢...(7/17 付)
-
鹿児島、宮崎両県にまたがる...(7/16 付)
-
石破政権が2月に閣議決定し...(7/15 付)
-
自民党派閥の裏金事件が表面...(7/13 付)
-
民主政治を正常に機能させる...(7/12 付)
-
陸上自衛隊は輸送機V22オ...(7/11 付)
-
トランプ米大統領が石破茂首...(7/10 付)
-
近代日本は、ほぼ10年おき...(7/9 付)
-
鹿児島県など多くの地方にと...(7/8 付)
-
給付か減税か-。賃金上昇を...(7/6 付)
-
2020年7月、九州地方を...(7/5 付)
-
トカラ列島近海を震源とする...(7/4 付)
-
参院選は本来、政権選択の選...(7/3 付)
-
激しいせきの発作が長期間続...(7/2 付)
-
日本の大型ロケット「H2A...(7/1 付)
-
戸籍の氏名に読み仮名を付け...(6/29 付)
-
原発から出る高レベル放射性...(6/28 付)
-
1945年6月26日、第2...(6/27 付)
-
攻撃の応酬を続けていたイス...(6/26 付)
-
鹿児島県議会の文教観光委員...(6/25 付)
-
超大国の米国がイランの核施...(6/24 付)
-
はじけんばかりの笑顔に心を...(6/22 付)
-
通常国会があす閉幕する。少...(6/21 付)
-
2023年12月の計画公表...(6/20 付)
-
カナダで開かれた先進7カ国...(6/19 付)
-
農林水産省は、コメ(水稲)...(6/18 付)
-
鹿児島市街地を火の海に包み...(6/17 付)
-
鹿児島市の山形屋が私的整理...(6/15 付)
-
米国を後ろ盾とするイスラエ...(6/14 付)
-
トランプ米政権の不法移民取...(6/13 付)
-
日本郵便が所有する全てのバ...(6/12 付)
-
東京電力福島第1原発事故は...(6/11 付)
-
梅雨前線が活発化している。...(6/10 付)
-
自宅で誰にもみとられずに亡...(6/8 付)
-
天皇、皇后両陛下と長女愛子...(6/7 付)
-
もくもくと湧き上がった巨大...(6/6 付)
-
鹿児島県が、鹿児島港本港区...(6/6 付)
-
尹錫悦(ユンソンニョル)前...(6/5 付)
-
長嶋茂雄さんがきのう89歳...(6/4 付)
-
陸上自衛隊が保有する米国製...(6/3 付)
-
年金制度改革法案がおととい...(6/1 付)
-
罪を犯した人に科す刑罰のう...(5/31 付)
-
外為法違反(無許可輸出)罪...(5/30 付)
-
イスラエル軍はパレスチナ自...(5/29 付)
-
小泉進次郎農相は、政府備蓄...(5/28 付)
-
国の特別機関である日本学術...(5/27 付)
-
鹿児島空港の駐車場が連休や...(5/25 付)
-
今国会の焦点となっていた選...(5/24 付)
-
ガソリン価格の抑制を狙った...(5/23 付)
-
価格高騰が続くコメを巡り「...(5/22 付)
-
九州電力が新たな原発の建設...(5/21 付)
-
職場での男女の平等を目指す...(5/20 付)
-
学びの質の向上に向け、デジ...(5/18 付)
-
消費税減税の是非が、夏の参...(5/17 付)
-
民間医療搬送用ヘリコプター...(5/16 付)
-
1945年に太平洋戦争が終...(5/15 付)
-
貿易を巡り激しく対立してい...(5/14 付)
-
新型コロナウイルス感染症が...(5/13 付)
-
軍事衝突が続いていたインド...(5/11 付)
-
政府の年金改革関連法案が来...(5/10 付)
-
自民党の西田昌司参院議員が...(5/9 付)
-
ナチス・ドイツが無条件降伏...(5/8 付)
-
鹿児島市のマリンポートかご...(5/7 付)
-
鹿屋市にあった旧日本海軍の...(5/6 付)
-
気温が上がる日が増え、熱中...(5/4 付)
-
政府が引き起こす恐ろしい戦...(5/3 付)
-
水俣病の犠牲者慰霊式に合わ...(5/2 付)
-
この春、社会人としてスター...(5/1 付)
-
50年前のきょう、ベトナム...(4/30 付)
-
選挙ポスターに品位保持規定...(4/29 付)
-
巨額の資金が政策決定をゆが...(4/27 付)
-
乗客106人と運転士が死亡...(4/26 付)
-
コメの価格高騰に歯止めがか...(4/25 付)
-
80年前の沖縄戦を指揮した...(4/24 付)
-
世界のカトリック教会の頂点...(4/23 付)
-
育児、介護と仕事の両立を支...(4/22 付)
-
有罪が確定した裁判をやり直...(4/20 付)
-
トランプ米大統領の関税政策...(4/19 付)
-
陸海空3自衛隊を一元的に指...(4/18 付)
-
違法なオンラインカジノが国...(4/17 付)
-
都城市で野生イノシシ1頭の...(4/16 付)
-
熊本地震の「前震」発生から...(4/15 付)
-
JR肥薩線の八代-人吉間(...(4/13 付)
-
山から立ち上る白煙や火柱。...(4/12 付)
-
サイバー攻撃に先手を打って...(4/11 付)
-
トランプ米政権による「相互...(4/10 付)
-
突然の戒厳令に端を発した政...(4/9 付)
-
1945年の春、沖縄周辺の...(4/8 付)
-
あしたは鹿児島県内のほとん...(4/6 付)
-
東海沖から九州沖に連なる震...(4/5 付)
-
トランプ米政権は「相互関税...(4/4 付)
-
元タレントの中居正広氏と女...(4/3 付)
-
一般会計の歳出(支出)総額...(4/2 付)
-
鹿児島、宮崎両県にまたがる...(4/1 付)
-
ミャンマー中部で28日、マ...(3/30 付)
-
同性同士の結婚を認めない法...(3/29 付)
-
沖縄県の慶良間諸島は、那覇...(3/28 付)
-
文部科学省が解散命令を請求...(3/27 付)
-
来月から鹿児島県内で鉄道、...(3/26 付)
-
石破内閣の支持率が急落し、...(3/25 付)
-
トランプ米大統領がロシアの...(3/23 付)
-
斎藤元彦兵庫県知事を巡るパ...(3/22 付)
-
イスラエル軍がパレスチナ自...(3/21 付)
-
「警視庁から各局-。日比谷...(3/20 付)
-
社会一般とはかけ離れた永田...(3/19 付)
-
鹿児島市吉野町の磯地区にJ...(3/18 付)
-
国民スポーツ大会(旧国民体...(3/16 付)
-
「くるぞ、万博。」のキャッ...(3/15 付)
-
トランプ米大統領と、ウクラ...(3/14 付)
-
桜島と鹿児島市街地を結ぶ桜...(3/13 付)
-
日本学術会議を現在の「国の...(3/12 付)
-
2011年の東日本大震災か...(3/11 付)
-
鹿児島県は、2025年度当...(3/9 付)
-
女性の地位向上を目指し、国...(3/8 付)
-
核兵器禁止条約の第3回締約...(3/7 付)
-
政府の2025年度予算案が...(3/6 付)
-
奄美大島と徳之島だけに生息...(3/5 付)
-
大統領同士の怒鳴り合いが、...(3/4 付)
-
欧州各国において、「自国第...(3/2 付)
-
高校授業料の無償化について...(3/1 付)
-
裁判のやり直し(再審)を認...(2/28 付)
-
ロシアのウクライナ侵攻開始...(2/27 付)
-
昨年11月の兵庫県知事選を...(2/26 付)
-
鹿児島県が鹿児島市の本港区...(2/25 付)
-
九州電力川内原発1、2号機...(2/23 付)
-
九州電力川内原発(薩摩川内...(2/22 付)
-
コメ高騰への対処策として、...(2/21 付)
-
2024年の荒茶の生産量で...(2/20 付)
-
組織一丸となって気を引き締...(2/19 付)
-
国会は2025年度予算案の...(2/18 付)
-
選択的夫婦別姓の導入可否を...(2/16 付)
-
トランプ米大統領がロシアの...(2/15 付)
-
いよいよあす、鹿児島県下一...(2/14 付)
-
ボランティアが支えるはずの...(2/13 付)
-
2023年の鹿児島県の農業...(2/12 付)
-
介護事業者の苦境が著しい。...(2/11 付)
-
石破外交の行く末を占う試金...(2/9 付)
-
鹿児島県は総額8527億円...(2/8 付)
-
2025年度予算案の国会審...(2/7 付)
-
基本構想の段階での見積もり...(2/6 付)
-
森友学園への国有地売却を巡...(2/5 付)
-
6人で争われた西之表市長選...(2/4 付)
-
鹿児島県内で2024年に起...(2/2 付)
-
聴覚障害のある女児は、将来...(2/1 付)
-
埼玉県八潮市で道路が陥没し...(1/31 付)
-
2025年春闘が事実上、幕...(1/30 付)
-
元タレントの中居正広さんと...(1/29 付)
-
1人で暮らす高齢者が増えて...(1/28 付)
-
今年は国連が定めた「国際協...(1/26 付)
-
通常国会が召集された。安倍...(1/25 付)
-
任期満了に伴う西之表市長選...(1/24 付)
-
日米地位協定に関して、47...(1/23 付)
-
「私がこのような歴史的な政...(1/22 付)
-
タレント中居正広氏の女性と...(1/21 付)
-
唯一の戦争被爆国として日本...(1/19 付)
-
イスラエルとイスラム組織ハ...(1/18 付)
-
6434人の死者を出した阪...(1/17 付)
-
韓国の尹錫悦(ユンソンニョ...(1/16 付)
-
巨大地震の可能性が格段に増...(1/15 付)
-
平和外交の象徴が世を去った...(1/14 付)
-
鹿児島県は鹿児島港に入港す...(1/12 付)
-
インフルエンザへの警戒が続...(1/11 付)
-
1966年の静岡県一家4人...(1/10 付)
-
勤め先の不正を告発し、正そ...(1/9 付)
-
石破茂首相は、現職首相が新...(1/8 付)
-
バイデン米大統領が、日本製...(1/7 付)
-
石川県の能登半島を襲った大...(1/6 付)
-
居ながらにして、欲しい知識...(1/5 付)
-
あとから振り返った時、日本...(1/4 付)
-
「地方創生」の旗が振られて...(1/3 付)
-
まど・みちおさんは、優しく...(1/1 付)
-
県民の安心安全を守る警察行...(12/31 付)
-
元日の能登半島地震に始まり...(12/29 付)
-
交流サイト(SNS)で犯罪...(12/28 付)
-
少子化や共働き世帯の増加な...(12/27 付)
-
JR九州が30年以上にわた...(12/26 付)
-
ホンダと日産自動車が経営統...(12/25 付)
-
自民、公明の与党が2025...(12/24 付)
-
経済産業省が2040年度を...(12/22 付)
-
北九州市のファストフード店...(12/21 付)
-
米国のトランプ次期大統領の...(12/20 付)
-
使途公開の不要な政策活動費...(12/19 付)
-
ソーシャルメディアが選挙戦...(12/18 付)
-
鹿児島と屋久島を直通で結ぶ...(12/17 付)
-
発がん性が懸念される有機フ...(12/15 付)
-
韓国の最大野党「共に民主党...(12/14 付)
-
政府が提出した2024年度...(12/13 付)
-
「核のタブー」が壊されよう...(12/12 付)
-
内戦下のシリアで反体制派が...(12/11 付)
-
公的医療保険には、重い病気...(12/10 付)
-
鹿児島県が、「魅力ある県立...(12/8 付)
-
83年前のあす12月8日、...(12/7 付)
-
軽くて丈夫、しかも安い。プ...(12/6 付)
-
韓国の尹錫悦(ユンソンニョ...(12/5 付)
-
ウクライナのゼレンスキー大...(12/4 付)
-
健康保険証は新規の発行が停...(12/3 付)
-
日米共同統合演習(キーン・...(12/1 付)
-
自民、公明両党が衆院選で大...(11/30 付)
-
イスラエルとレバノンの親イ...(11/29 付)
-
続く失敗に衝撃は大きい。宇...(11/28 付)
-
アゼルバイジャンで開かれて...(11/27 付)
-
鹿児島市長選挙で現職の下鶴...(11/26 付)
-
悪質事故で大切な人を奪われ...(11/24 付)
-
鹿児島市の山形屋で開催中の...(11/23 付)
-
小中学校や小中一貫の義務教...(11/22 付)
-
出水市高尾野の養鶏場で死ん...(11/21 付)
-
兵庫県議会で全会一致の不信...(11/20 付)
-
衆院選を契機に「年収の壁」...(11/19 付)
-
任期満了に伴う鹿児島市長選...(11/17 付)
-
奄美市の奄美空港に米軍のオ...(11/16 付)
-
鹿児島県警のトップである本...(11/15 付)
-
鹿児島県で製造が盛んな本格...(11/14 付)
-
少子化に歯止めをかけるため...(11/13 付)
-
衆院選を受けた特別国会が召...(11/12 付)
-
指宿市の山川漁港に来年4月...(11/10 付)
-
先月の衆院選で女性の当選者...(11/9 付)
-
北朝鮮がロシアのウクライナ...(11/8 付)
-
米大統領選は、共和党候補の...(11/7 付)
-
会社や自治体などの組織に属...(11/6 付)
-
同性婚を認めない民法などの...(11/5 付)
-
東北電力女川原発2号機(宮...(11/3 付)
-
首都圏を中心に手口の類似し...(11/2 付)
-
大阪地検の検事正だった北川...(11/1 付)
-
文化の日を控えたあす、長年...(10/31 付)
-
衆院選で与党が歴史的大敗を...(10/30 付)
-
自民党の派閥裏金事件に不信...(10/28 付)
-
衆院選はきょう投票日を迎え...(10/27 付)
-
住民や観光客の移動手段が十...(10/26 付)
-
1986年に福井市の中学3...(10/25 付)
-
東京一極集中の是正と人口減...(10/24 付)
-
「政治にはカネがかかる」と...(10/23 付)