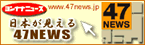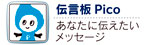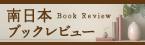【6日開幕 鹿児島全共】前回団体優勝の鹿児島、“初防衛戦”へ 肉の「おいしさ」評価する7区を新設
2022/10/04 10:00
九つの出品区に出場するのは、41道府県の牛飼いたちが手塩に掛けて育て上げた439頭。鹿児島でも24頭が県代表の座を射止めた。選び抜かれた漆黒の巨体は艶やかで美しく、凛(りん)とした立ち姿からは気品さえ漂う。
いざ「日本一」へ-。和牛王国の威信を懸けた決戦は10月6日、霧島市と南九州市を舞台に幕を開ける。
■脂肪の質、生産性高める
全国和牛登録協会(京都府)・向井文雄会長(72)に聞く
主催する全国和牛登録協会(京都府)の向井文雄会長(72)に、歴史や意義、今後の改良の方向性を聞いた。
-全共のあゆみは。
「初めて開催されたのは1966年で、当時の和牛は基本的に農耕や運搬を担う役用だった。しかし、高度経済成長期でトラクターなど農業機械が登場し、和牛は“リストラ”の危機にさらされる。第1回大会のテーマは『和牛は肉用牛たりうるか』。肉用牛として残していく道筋を付けることを目指した」
「次の転機は91年の牛肉の輸入自由化。安い外国産と戦わなければならなくなり、差別化のためにサシ(霜降り)を重視するようになった。2007年の鳥取全共以降は、遺伝的多様性の確保に向け、地域の特色を持つ牛の掘り起こしを進めている。今大会でも、この方向性は維持されている」
-鹿児島大会の特徴は。
「これまでと大きく変わるのは、肉の“おいしさ”を評価するための7区を新設した点だ。サシの量だけでなく質の高さを求め、おいしい肉の作り方や評価手法の確立を目指す。やはり和牛は食べ物だという原点に返ることが必要だ。将来的には、味を左右するさまざまな成分を含めた遺伝的な改良や、測定の技術の向上が進むと期待している。この取り組みは始まったばかりで、どの道府県も首席を狙えると言えるかもしれない」
「現在進行形で問題になっているのは飼料高騰。子牛生産では1年1産の確立、肥育では少ない餌でも増体を良くするなど、生産性を向上させなければならない。これらすべてを合わせたものが大会テーマにある『和牛力』だ」
-特別区「高校および農業大学校の部」が常設される。
「農家数が減る中、担い手の育成は重要だ。全国の学生がベテラン農家と同じ舞台で戦うことで交流し、互いに刺激を与え合う機会にしてほしい。本戦出場は24校を見込むが、予選を含めると全国数十校が参加する。牛づくりは人づくり。全共が若手にとって一つの目標になったらうれしい」
-全共の果たすべき役割は。
「単に順位にこだわるのではなく、そこを目指し、注いできた努力や費用、時間を無駄にせず今後の和牛生産に生かしてほしい。改良を進めていくには、現場にいる農家の日々の取り組みこそが重要だからだ」
-開催県・鹿児島に期待することは。
「鹿児島は全国に子牛を出荷する日本一の産地。繁殖雌牛の基盤にもなっている。大会を通して、改良方法の手本を全国に示してくれることを期待している」
■むかい・ふみお 1973年神戸大学農学部卒業。85年、京都大学農学博士。神戸大学・大学院教授などを経て、2008年から現職。神戸大学名誉教授。