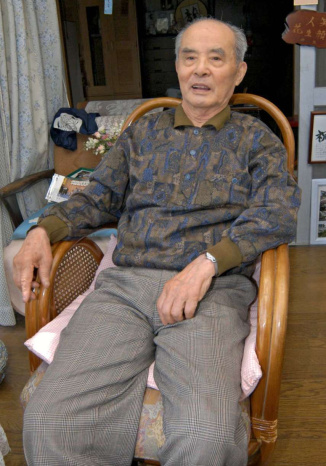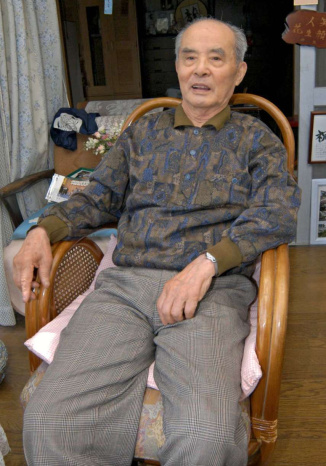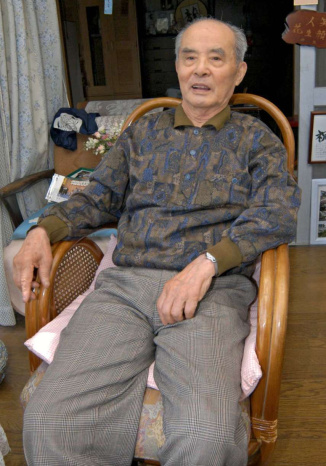
終戦直後の2カ月半、ソ連兵に連行された経験を話す中村甚治さん
■中村甚治さん(83)南種子町中之上
一九四一(昭和十六)年に旧制種子島中学卒業後、満州に渡り満州航空の無線通信士としてチチハル飛行場で働いていた。四四年に陸軍の通信部隊・第七五八八部隊に入隊。終戦はハルビンで迎え、八月十六日には武装解除と部隊解散式があった。身寄りのないものは隊長とともに行動するように言われたが、私は新京にあった満州航空本社に帰ることにして隊を離れた。
しかし、ハルビン市内はすでにソ連兵が進駐してきており動きが取れず、日本人が集まっているという映画館に行った。軍人だと分かると捕まると思い、軍服を一般の服に着替え倉庫に隠れたが、発見された。裸にされ銃で小突かれたが抵抗しないと一般人と認められたようだ。
映画館には百人ほどの日本人がいたが、そのうち比較的元気な男性だけ約五十人集められ突然移動を命じられた。一カ所に集めておくと暴動の恐れがあるというソ連側の判断だったようだ。「命令に従わないものがいたら、全員を銃殺する」といわれ、数人のソ連兵に監視されながらの移動が始まった。
行き先も知らされず、食事もなく、ただ指示される方向に歩くだけの移動。満州は九月に入ると朝晩の冷え込みが厳しくなるが、服装は夏のままなのでみんなで寄り固まって寝た。若い人が外側、年配者が内側で円陣を作り、互いに暖を取り合った。食事は歩く途中の畑から盗んだ。カボチャやネギ、ニンジンなどを生のままかじった。
一カ月かかって牡丹江に到着。護国神社に数日いたが、神社は見る影もなく荒らされていた。休む間もなく、その日の食べ物探しに明け暮れていた。
しばらくしてまた移動。寒さや飢えに加え、意味がなく、終わりのない行軍に次第に思考がまひしてきた。行軍の途中、死んだ人や落後した人もいたが、その人たちのことを考える余裕もなかった。体中にシラミがわき、靴や衣服もぼろぼろ。行軍二カ月をすぎたころには、ほとんどの人が死ぬ覚悟ができていた。
チャームースーに移動後、歩けない人が多くなり、みんなで抱き合って「ここで殺してくれ」と頼んだ。生きていく希望もなく、肉体的にも精神的にも極まった状態だったと思う。毎日の状態を見ていたソ連兵は、上部との交渉の結果、新京で解放してくれた。
これまでの人生であれ以上の経験はない。引き揚げ船から見た種子島はただぼんやりしていたことだけを覚えている。
(2006年5月11日付紙面掲載)