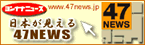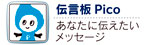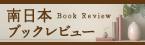樋之口里花氏
【知事選アンケート】樋之口里花氏の回答
2024/07/01 10:20
Q ドルフィンポート跡地への新総合体育館計画について、景観面や膨らむ事業費を理由に反対する声があります。どう考えますか。
体育館の老朽化と子どもたちのスポーツ環境を守るという点で新体育館の必要性は理解できるが、現行計画が本当に適切なのかは疑問。まず、ドルフィンポート跡地への建設は桜島の景観を損ないかねず、鹿児島観光に悪影響で、事業費もさらに増える。また、国際大会の誘致を見据えているが、誘致できるのか疑問。今の計画を強行すれば、負の遺産を生み出す。議論の積み重ねも尊重しつつ、より多くの県民が納得する施設整備が必要。
Q 中山間地の小規模農家のためにどんな政策を展開しますか。
県内の中山間地は農家数や農業産出額の多くを占める。農産物の価格保障と農家の所得補償で農家を守ることが必要。国の「中山間地農業ルネッサンス事業」などを活用し、地域の要望を聞きながら最善の施策を展開する。
Q 政治家を目指すきっかけは何ですか。
子ども医療費窓口無料化などの要求を行政に届けてきました。その要求を実現する道を開きたいと思いました。
Q 川内原発が運転延長されます。九電や国とはどのようなスタンスで向き合いますか。
地震大国日本でさらに20年も原発を動かせば、いつ大事故が起きてもおかしくない。能登半島地震では大半の避難ルートが通行不能になった。使用済み燃料貯蔵プールも約6年で満杯。使用済み燃料の行き場はなく、鹿児島が最終的な核のごみ捨て場になりかねない。
私個人は運転延長には反対だが、賛成の意見もあるので、県民投票を実施する。その結果を最大限尊重し、国や九電、関係市町村と対話し、必要な対応をとる。
Q 水俣病の早期解決に向け、県として何ができますか。
不知火海沿岸に居住歴がある全住民の健康調査を実施するよう国に強く求める。15年前に法律で明記された健康調査が実施されていないことから、県独自の健康調査を実施できないか、専門家を交え調査手法を検討する。
Q リーダーシップ、親しみやすさ、行動力、聞く力-。知事に最も求められる資質は。
「国策だから」と国にモノ言わないのではなく、県民の代表として国にモノを言えることです。
Q 南西諸島で自衛隊の防衛力強化が進んでいます。どう考えますか。
防衛力を強化することで私たちの安全が守られるとは思えない。真っ先に狙われるのは軍事施設。軍備強化ではなく、憲法9条の理念にのっとり、アジア諸国との文化スポーツ交流、経済交流、学術交流などの民間交流をさらに進め、相互理解を深めていくべき。
私たちの命や暮らしにかかわる大事なことが勝手に決められている。基地建設がどういう事態を招くのかについての情報を県民と共有した上で県民投票を実施する。
Q 県の財政運営の現状と今後の在り方について考えを聞かせてください。
各事業で当初予算を使い切れずに返納または繰り越す状況が続いている。事業継続の観点から前年度予算を踏襲して予算編成が行われているが、これを見直し、県民生活に直結する事業について必要な予算を計上する。
Q 10代の若い有権者、子どもたちにお薦めしたい本は。
奴隷制度下の黒人を描いた「アンクル・トムの小屋」(ハリエット・ビーチャー・ストウ著)
Q 人口減少が止まりません。2023年の出生数は1万人を切りました。どんな対策が必要ですか。
子ども医療費▽ひとり親家庭医療費▽重度心身障害者医療費-の窓口無料化や給食費無償化、生理の貧困対策として全学校のトイレに生理用品を配備し、パートナーシップ宣誓制度を導入する。雇用が不安定で給料が少なければ、子どもを持ちたくてもためらうのは当然。まずは県が率先して、県職員の正規雇用への流れをつくる。「誰もが尊厳をもって安心して生きることができ、人が人として大切にされる県政」をつくる。
Q 県内でもプロスポーツが盛んになってきました。県としてどのように支援しますか。
サッカーJ1やバスケットボールB1には施設基準があり、現状では基準を満たしていないことは承知している。ともにホームタウンは鹿児島市であり、鹿児島市と密に連携をとり、必要な支援を検討する。
Q 無人島に何か一つだけ持って行くとしたら? 理由も。
おにぎり。おなかがすいたら動けません。
Q インバウンドを含め観光分野でどんな戦略を描いていますか。
鹿児島銀行の建物が新しくなり、ショックを受ける観光客もいる。都会にもあるような施設整備ではなく、先人が築き上げてきた文化を生かすことが重要。しかし、公共交通機関がなく通院できないために、生まれ育った地域を去らなければならない人もいる。人がいなくなれば、文化はなくなる。文化を守るためにも、市町村や関係事業者と連携して地域バス路線やJRローカル線を維持し、国の支援も強く求めていく。
Q 地方の県立高校で定員割れが続いています。県としてどう対応しますか。
県立高校の序列化をなくし、進学を希望する生徒もそうでない生徒も地元の高校に通えるようにすべき。地域に暮らし続けられる地域づくりを進めるべき。
Q 最近うれしかったことは?
会いたかった同級生に30年ぶりに偶然出会ったことです。