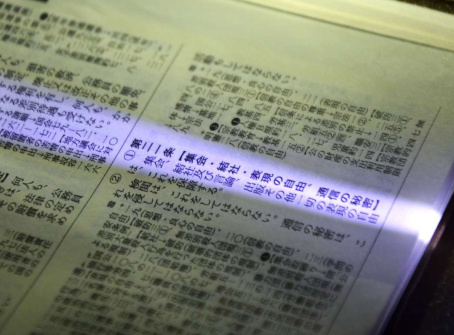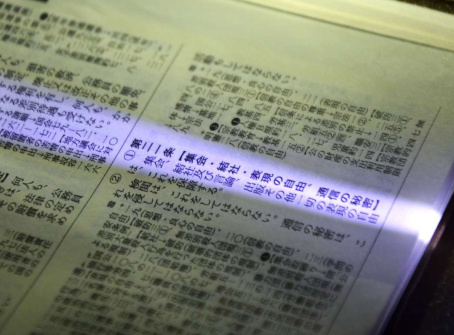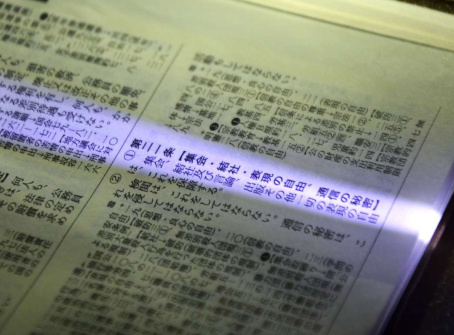
憲法21条で保障される「表現の自由」
鹿児島県警の情報漏えい事件を巡り、県警は福岡市のウェブメディアを家宅捜索した。取材活動に従事する記者にとって、「取材源の秘匿」は堅守すべき鉄則であり、それを脅かす事態となっている。警察権力の暴走か適正な捜査か-。連載「検証 鹿児島県警」の第3部は、一連の経緯や海外の事例を通し、メディア捜索の是非を考える。(連載・検証 鹿児島県警第3部「メディア捜索の波紋」③より)
鹿児島県警のウェブメディアへの家宅捜索は、その是非を巡ってジャーナリズム教育の現場でも題材になった。専修大学文学部ジャーナリズム学科では2024年度、山田健太教授(65)が「言論法」の授業で「取材源秘匿の重要性」と題し講義。ゼミでも取り上げ、議論を促した。
授業とゼミでは「記者と取材源の信頼関係を公権力が破壊した構図。報道の自由が侵害されている」と解説した。記者と情報提供者との間に取材源は明かさないという信頼があってこそさまざまな情報が寄せられることから、「国民の知る権利を守るためにも取材源の秘匿は重要だと学ぶ格好の事例だ」と語る。
ゼミ生(22)は「取材源を警察が特定したのは乱暴だ」と批判する。その半面、「今回は警察官が情報を漏らしている。被害者にとっては大事件で、県警が調べないのも不自然。一方的に悪いとも思えない」。
■ □ ■
取材で得られた情報はどこまで守られるべきか-。過去には裁判所が公判を審理する上で、証拠として出す必要があると判断した例もある。
1969年、福岡地裁は学生と機動隊が衝突した「博多駅事件」の現場を撮影したフィルムを提出するようテレビ局に命じた。90年には、暴力団組員による取り立ての様子を捉えた、放送済みのビデオテープを警視庁が押収した。テレビ局側は「報道の自由に支障をきたす」と提出を拒んだり、押収は認められないと裁判所に訴えたりしたが、最高裁はいずれも棄却した。
両決定は、憲法21条の保障下にある報道の自由は尊重されるべきであり「報道機関の不利益が限度を超えないよう配慮されなければならない」とした。その上で「公正な裁判のためには、報道の自由がある程度制約を受けることも否定できない」と示した。
取材で得た情報の目的外使用を禁止する法規定は、現在存在しない。捜査の必要性と報道の自由を「比較衡量すべき」との考えが基礎にある。
■ □ ■
家宅捜索を巡る見解は識者の間でも割れている。
刑事訴訟法に詳しい北海道大学名誉教授の白取祐司弁護士(72)=東京都=は「今回のケースは約300人の被害者がおり、プライバシー保護の観点から看過できない。証拠収集のためにはやむを得ない」との見方だ。判例も念頭に「判断が著しく不当とはいえない」と判断している。
一方の山田教授は「家宅捜索で証拠を押収するだけでなく、取材源の特定にまで及んだという事例はこれまでに聞いたことがない」と指摘。明らかな告発者つぶしだと訴え、「69、90年の事案とは決定的に異なる。公権力による報道機関への捜索を許す風潮を生む前例とならないか、深く憂慮している」と話した。