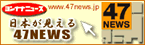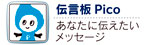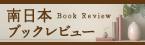「最後の一滴まで注いで」と語る柚木原拓朗さん=鹿児島市谷山中央2丁目の「お茶のかおり園」
①冷ます②蒸らす③数回に分ける…日本茶インストラクター直伝、急須でおいしくお茶を入れるコツ
2025/05/06 16:59
若者世代を中心にリーフ茶離れが進む一因として、急須を使う難しさが挙げられる。ただ、日本茶インストラクター協会鹿児島県支部の柚木原拓朗支部長(51)=お茶のかおり園店長=は「正しく入れると、価格以上のうまさを引き出せる」と急須の魅力を発信する。誰にでもできる、おいしいお茶の入れ方を聞いた。
柚木原支部長によると、小さめの急須で2杯が目安になる。手順は(1)湯飲みに湯を注ぎ湯気が立たなくなるまで冷ます(2)急須に湯と茶葉を入れ40秒~1分間ほど蒸らす(3)濃さが均一になるよう、数回に分けて入れる-の3段階。コツは「手首のスナップを使い、テンポ良く入れること」。急須の中を転がし、湯と茶葉を十分に混ぜるという。
新茶では、新芽の裏に生える「毛茸(もうじ)」が浮いている様子を目でも楽しめる。柚木原支部長は「茶種や急須ごとに入れ方は違う。まずは気軽にお茶屋に足を運んで相談してみてほしい」と呼びかける。
■生産は好調、でも消費は伸び悩む
鹿児島県は、戦後の昭和40年代から茶業を本格化した後発産地だ。大規模栽培に適した平たん地という特色や、松元機工(南九州市)が全国に先駆けて開発した乗用型摘採機などを生かして、生産量拡大に取り組んできた。
これらの成果もあり、1次加工後の荒茶生産量は、2024年産で2万7000トンと、初めて王者・静岡県(2万5800トン)を抜いて日本一となった。
農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)や県農業開発総合センターの協力もあり、多品種がそろうのも特徴の一つ。国内栽培面積の約7割を占める「やぶきた」の割合は全国で最も低く、20品種以上が栽培されている。
23年度時点で海外需要の高いてん茶(抹茶原料)は1585トン、紅茶は194トンといずれも全国トップ。国内人口が減少する中、海外輸出拡大も視野に入る。
生産面が好調な一方、県内の消費は伸び悩む。総務省家計調査によると、鹿児島市のリーフ茶の年間消費額は22~24年は平均4384円で、県庁所在地などの中で全国8位。トップの静岡市の半分程度しかない。
県茶業会議所の光村徹専務理事(62)は「生産量では日本一になったが、消費量拡大という最大の課題が残っている。まずは茶のおいしさを知ってもらい、県内に“お茶マニア”を増やしたい」と話した。