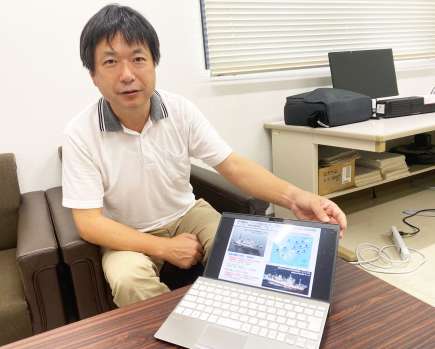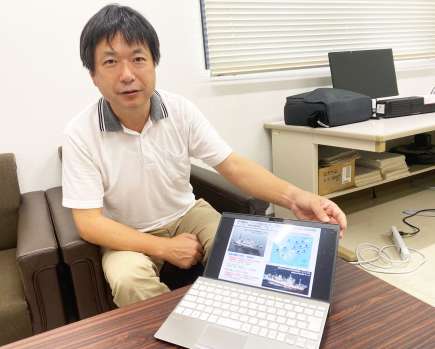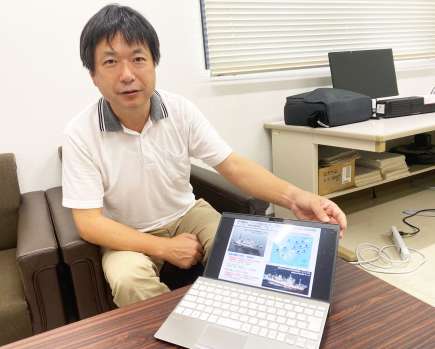
トカラ列島群発地震の調査概要を説明する八木原寛鹿児島大学准教授=9日、鹿児島市の鹿児島大学南西島孤地震火山研究所
群発地震が続く鹿児島県のトカラ列島で、鹿児島大学南西島弧地震火山研究所の八木原寛准教授(火山学・地震学)を研究代表者とした総合調査が行われている。東京大や海洋研究機構など8機関が参加。海底に地震計を投入して群発地震の正確なデータを収集、解析する。
八木原准教授によると、九州本土までは高密度の地震観測網があるが、南西諸島は観測点が少ないため、地震活動の把握が難しく、震源の位置も正確には分かっていない。震度計は十島村の各島にあるものの、地震計のある観測点は中之島と宝島のみ。奄美大島の2カ所を加えた4つの観測点で震源域を推定している。
気象庁の観測点のほか、鹿大は悪石島、平島、小宝島に地震計を設置し、気象庁のデータと合わせ、震源分布のばらつきを改善した。今回の調査ではより正確に把握するため、悪石島~小宝、宝島の海域に海底地震計を10個設置。陸上の観測点もリアルタイムでデータを受信できるようオンライン化した。
調査は文部科学省の科学研究費助成事業(科研費)1800万円を使い、8月に開始。海底地震計は11月に回収し、データの補正処理を経て12月に解析を始める。このほか人工衛星を使って地殻変動を調べる地点を増設、住民の避難行動の実態なども調べる。
八木原准教授は「地震は直上で観測するのが基本だが、海域の場合はそれができなかった。まずは海底地震計の回収を成功させ、公表できる成果を出したい」と話す。ただ今回の調査は地震活動が低下して以降のもので理想は群発地震の初期段階からのデータ取得。トカラ列島近海で繰り返し発生してきた地震の原因解明には、継続した調査が必要になる。