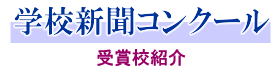中学校の部
1席
小宿中
むじらしゃ新聞
 |
| 1席に輝いた小宿中生徒会の生徒ら |
「むじらしゃ新聞」と昨年12月に改題し、1年足らずで1席に輝いた。編集長の3年、川畑優輝さんは「『むじらしゃ』とは島口(島の方言)で『面白い』の意味。読んだ人にそう思ってもらえれば、との願いを込めた」と説明する。
生徒会の有志7人が原則月1回、B4判両面の新聞を発行する。生徒会のスローガン「We love 小宿」を冠した特集記事に力を入れる。生徒会のメンバーが演じた即興劇「ソシオドラマ」の様子などを紹介。「自分たちが暮らす小宿地区や奄美を好きになってほしい」と訴える。
「人」を表す島口の「ちゅ」と銘打ったコーナーでは、学校行事で活躍した生徒や新たに赴任してきた教諭らを取り上げた。一問一答式のインタビューに写真を載せ、人となりや思いが伝わるよう工夫を凝らす。
昼休みに打ち合わせや取材を重ね、放課後などにタブレット端末でそれぞれ執筆する。共有ホルダーに原稿を入れ、上妻恵美教諭(44)が手を入れる。川畑さんを中心にレイアウトや見出しを練ってきた。
上妻教諭は「よりよい新聞を一緒に作ろうという気持ちが紙面に表れた」と喜んだ。
2席
福平中
福風新聞
 |
| 2席を獲得した福平中学校の生徒会役員ら |
校内行事や生徒会活動を中心に取り上げ、毎月約570部を発行する。扱うテーマの決定から取材と撮影、執筆までを生徒会役員21人が交代で担う。
入学式や長縄大会を取り上げた記事では、雰囲気が伝わるように場面の描写まで盛り込んだ。夏休み前には、シート状制汗剤を校内で使う際のルールを紹介したり、養護教諭に熱中症対策を尋ねたりするなど、季節に合わせた話題も充実させている。
教員が担ってきた編集作業も、2学期からは中心メンバーの5人が手がける。文章の長さや写真の大きさを調整し、余白にイラストを載せるなど、試行錯誤しながら紙面を作り上げる。
3回連続の入賞に3年生は感慨もひとしお。生徒会長の福元岬さんは「大変だったが達成感は大きかった」。副会長の山口優奈さんは「みんなで協力した編集作業は、かけがえのない時間」と振り返る。副会長の西田樹さんは「国語が苦手だったけど、言葉を選ぶ感覚が身についた」と感謝した。
3席
樋脇中
積極一歓
 |
| 初の受賞となった樋脇中学校の生徒たち |
学校新聞は1973年に創刊。一時途絶えたり、名称を変えたりしながら書き継がれてきた。生徒会が現体制になった昨秋、現在の2、3年生12人全員で製作することを決めた。
月1回発行。生徒や教員、地域に配る。学校行事などを取り上げるメイン記事のほかに、全校生徒139人へのアンケート結果や教員のインタビュー、4こま漫画を掲載。好きな卒業ソングや期末テスト特集といった、その時期ならではの話題も紹介する。武田健教諭(36)は「読み手のことを考えてテーマを選ぶようになった」と評価する。
簡潔な文章やグラフを入れるなどして、読みやすい紙面作りに工夫を凝らす。校内の合唱コンクールを取材した3年坂上菜々さんは「記事を書くのは難しかったが、成功した様子をうまく表現できた」。
初の受賞に、生徒たちは「取れたらいいなと思っていた。まさか実現するなんて」と喜びを隠さない。来年は、さらに上の賞を取ってほしいと後輩たちに期待する。
高校の部
1席
大島高
大高ジャーナル
 |
| 6回連続の1席に輝いた大島高校新聞部 |
2018年12月の創刊から奄美群島の本土復帰運動を扱う。コンクールに出品した第19号は、70年の節目を記念した特集面を展開。当時を知る関係者のインタビューなどを通して、歴史や記憶を後世につなぐ意義を探り、6回連続の1席に輝いた。
復帰運動への関心を尋ねたアンケートは、生徒を中心に約160人から回答を得た。9割超が「よく知らない」「詳細は分からない」という結果だった。
新聞部部長の2年、加藤笹月さんは「今伝えなければ記憶が薄れてしまうと思った。目標だった6連覇を達成できてうれしい」と喜ぶ。取材前は部員も詳しくなく、過去の新聞や資料を読み込んだという。
部員は8人。週2回、放課後に活動する。校内だけでなく、地域の公民館や同窓会にも配布する。2年、大野清志郎副部長は「島を離れた卒業生にも学校や地域の日常を知らせ、懐かしく感じてもらいたい」
中学生の頃に大髙ジャーナルを読んで進学を決めた1年、山下蓮さんは「分かりやすい文章を書くのが目標。より見やすくなるよう写真やイラストを増やし、来年も1席を取りたい」と語った。
2席
松陽高
松陽スピリット
 |
| 創立1年目で2席に輝いた松陽高校新聞同好会のメンバー |
本年度に創刊し、早くも2席を獲得した。学校行事や生徒紹介のほか、学校がある旧松元町の話題も掲載。地域との架け橋になる新聞作りに励む。新聞同好会の3年、浦乃愛部長は「初参加で受賞できてうれしい」と笑顔だ。
週2日の企画会議で紙面のテーマを検討し、学期ごとに発行する。7月号では、生徒会による地域の名産・松元茶の販売や、学校近くの池に生息する特定外来種の調査など、校外での活動も取材。3年、梶木詩桜(しおん)さんは「『初めて知った』との反響も多く、達成感がある」と満足そうだ。
他校で新聞部を立ち上げた経験のある池之上博秋教諭(51)が呼びかけ、4月に同好会が発足。部員17人は取材経験がなかったが、クオリティーの高い4こま漫画や、地域性に富んだ紙面が好評だ。
12月号からは1、2年生3人が中心となって製作する。新部長となる1年、立野美吹(みふい)さんは「目を引く紙面で読者も、新聞を作る仲間も増やしていきたい」と意気込む。
3席
甲南高
甲南髙校新聞
 |
| 3席に入った甲南高校生徒会広報委員会 |
毎年度2回発行する季刊のほか、号外もつくった。生徒会広報委員会の82人が分担して、テーマ決めや取材、執筆に当たった。
9月号の見出しは「不易と流行 甲南のいま」。生徒にアンケートを行い、学校生活で変わらない方がいいものや必要な変化などを調査。グラフを多用してまとめた。7月に発行した号外では、「もっともっと!! 先生のこと 知りたい!!」のテーマで教員ら8人の素顔に迫り、普段見えない姿を伝えた。
4年連続の2席を逃し、2年の濱村直史委員長は「さらに変化が必要だと感じた」と悔しがる。今夏、岐阜県であった全国高校総合文化祭(ぎふ総文)で他県の学校新聞に触れ、校内の話題だけでなく平和問題や災害、防災といった社会的テーマも扱う必要性を感じたと話す。
昨夏のかごしま総文と、ぎふ総文に参加した2年の坂下綾菜さんも刺激を受けた。「学んだことを今後に生かし、1席や2席が取れるようになりたい」と意欲を語った。
- ミナミさんちのNIE
- オセモコ
- よむのび教室・よむのびプラス案内
-
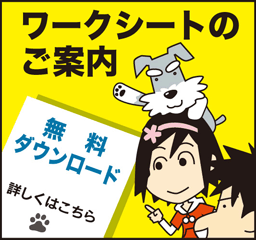
- ワークシート
-
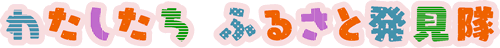
-
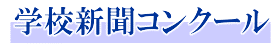
-

-
お子様の学習をサポート= 学力アップに新聞を =2020度から導入された「大学入学共通テスト」では、知識だけではなく、思考力、判断力、表現力が重視されます。 新聞を読むことで入試に必要な読解力や表現力のアップにつながります。お子さまの将来のために新聞を家庭教材として活用してください。
-
= 学校の授業で新聞活用が進んでいます =学習指導要領の改訂で、小・中・高校の授業で新聞活用がますます進んでいます。
南日本新聞には、こども新聞をはじめ子どもたちの国語力・読解力・作文力などの学力向上をサポートする紙面が満載です。